2009年06月02日
製茶の工程
新茶の季節も一段落して、6月になりました。
今度はもうしばらくすると二番茶の季節に入って行きます。
5月のブログでは、山から新茶を摘んできたところまでで終わっていました。
さあ、それを茶工場に運んできます。
その後はどのような工程になるでしょう。
ご紹介するのは熊本県山鹿市の茶工場です。
昨年大規模な拡張を行い、県下でも有数な茶工場となっています。
まず、摘んできた生葉をストックして、少しずつ「蒸し機」にベルトコンベアーで
流していきます。
この先で蒸気を使い、蒸していくわけです。
やはりベルトコンベアーで「蒸し機」の中をくぐらせていきます。
この蒸す時間をどのくらい取るかによって、できる茶の形が違ってきます。
蒸し機を通す時間を短めに(30~40秒)すれば形が硬くなり、長く取れば
葉の細胞膜が蒸気により壊され、葉が粉っぽく、お湯に出した時濃く出る
タイプのお茶になります。30~40秒を標準とすれば、その2~3倍長く蒸した
お茶を「深蒸し茶」と呼んだりします。
そして蒸し機の中から出た葉は上の方に上っていきます。そこから今度は
「粗揉機」と呼ばれる機械に入っていきます。ここで葉をほぐしながら粗く揉みます。
ここでは温風を当てながら茶葉の水分を均一に蒸発させます。
その後流されるのが「揉捻機」という機械です。機械ごとグルグル回っているものが
そうです。ここでも葉の水分を均一にするために圧力をかけながら揉んでいます。
さあ、次は「中揉機」を使った中揉みです。
ここでも温風を使い茶葉を軽く揉みながら乾燥を進めます。
そしてまた揉捻という風に何度も揉みを加えていきます。
おいしいお茶を作るためには「揉む」という作業はとても重要なのです。
最後に「精揉機」で精揉という工程をかけます。これは葉を針状に伸ばして
形を整える機械です。振り子のように動く部分で葉を真っ直ぐに伸ばしていきます。
この後さらに乾燥させ、ようやく「荒茶」と呼ばれるお茶が出来ます。
このように大規模な機械をいくつもくぐらせてお茶は製品として作られていきます。
このような機械も実は大元の原理は「手揉み」なのです。
いくつもの試行錯誤を重ね、機械は改良されていきました。
でもその中に手揉みのお茶の基本はしっかり息づいているのです。


今度はもうしばらくすると二番茶の季節に入って行きます。
5月のブログでは、山から新茶を摘んできたところまでで終わっていました。
さあ、それを茶工場に運んできます。
その後はどのような工程になるでしょう。
ご紹介するのは熊本県山鹿市の茶工場です。
昨年大規模な拡張を行い、県下でも有数な茶工場となっています。
まず、摘んできた生葉をストックして、少しずつ「蒸し機」にベルトコンベアーで
流していきます。
この先で蒸気を使い、蒸していくわけです。
やはりベルトコンベアーで「蒸し機」の中をくぐらせていきます。
この蒸す時間をどのくらい取るかによって、できる茶の形が違ってきます。
蒸し機を通す時間を短めに(30~40秒)すれば形が硬くなり、長く取れば
葉の細胞膜が蒸気により壊され、葉が粉っぽく、お湯に出した時濃く出る
タイプのお茶になります。30~40秒を標準とすれば、その2~3倍長く蒸した
お茶を「深蒸し茶」と呼んだりします。
そして蒸し機の中から出た葉は上の方に上っていきます。そこから今度は
「粗揉機」と呼ばれる機械に入っていきます。ここで葉をほぐしながら粗く揉みます。
ここでは温風を当てながら茶葉の水分を均一に蒸発させます。
その後流されるのが「揉捻機」という機械です。機械ごとグルグル回っているものが
そうです。ここでも葉の水分を均一にするために圧力をかけながら揉んでいます。
さあ、次は「中揉機」を使った中揉みです。
ここでも温風を使い茶葉を軽く揉みながら乾燥を進めます。
そしてまた揉捻という風に何度も揉みを加えていきます。
おいしいお茶を作るためには「揉む」という作業はとても重要なのです。
最後に「精揉機」で精揉という工程をかけます。これは葉を針状に伸ばして
形を整える機械です。振り子のように動く部分で葉を真っ直ぐに伸ばしていきます。
この後さらに乾燥させ、ようやく「荒茶」と呼ばれるお茶が出来ます。
このように大規模な機械をいくつもくぐらせてお茶は製品として作られていきます。
このような機械も実は大元の原理は「手揉み」なのです。
いくつもの試行錯誤を重ね、機械は改良されていきました。
でもその中に手揉みのお茶の基本はしっかり息づいているのです。


2009年05月21日
お茶はどうやって作られる?
前回、山のお茶の茶摘みの様子をお伝えしました。
では摘んできた生葉はどのように製品としてのお茶になるのでしょう。
まず、熱を加えて酸化酵素の働きを止め、しっかり揉みながら
乾燥させます。
言ってみればこれだけですが、この工程には昔からのたえまない工夫と
努力が加えられてきています。
それでは昔はどのようにお茶を作っていたのでしょう。
最初の「熱を加える」方法には2通りあります。
一つは釜で炒る方法です。これは釜炒り茶として現在も作られています。

これは矢部地方などで昔から作られている手釜で炒る釜炒り茶の製造写真です。
現在はこのような手釜で作られることはほとんどなく、炒り葉機と呼ばれる機械式の
釜炒り機械を使います。
もう一つが蒸気で蒸す方法。いわゆる煎茶などはこの方法をとり、全国で流通している
お茶のほとんどが蒸したお茶です。
昔は「せいろ」で蒸していました。

このような素朴な器具を使い蒸します。
さらに「ほいろ」と呼ばれる器具を使い、下から炭火で温めながら
揉んで乾燥させていきます。
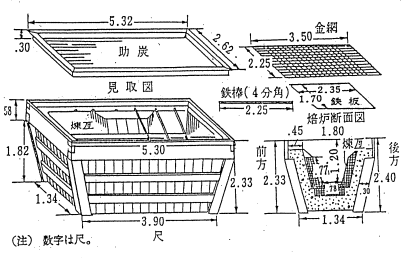

このように手間暇かけてお茶を作っていたのです。
さて、現在はどのようにお茶を作っているのでしょう。
それは次回に、茶工場の中をご案内いたします。

では摘んできた生葉はどのように製品としてのお茶になるのでしょう。
まず、熱を加えて酸化酵素の働きを止め、しっかり揉みながら
乾燥させます。
言ってみればこれだけですが、この工程には昔からのたえまない工夫と
努力が加えられてきています。
それでは昔はどのようにお茶を作っていたのでしょう。
最初の「熱を加える」方法には2通りあります。
一つは釜で炒る方法です。これは釜炒り茶として現在も作られています。

これは矢部地方などで昔から作られている手釜で炒る釜炒り茶の製造写真です。
現在はこのような手釜で作られることはほとんどなく、炒り葉機と呼ばれる機械式の
釜炒り機械を使います。
もう一つが蒸気で蒸す方法。いわゆる煎茶などはこの方法をとり、全国で流通している
お茶のほとんどが蒸したお茶です。
昔は「せいろ」で蒸していました。

このような素朴な器具を使い蒸します。
さらに「ほいろ」と呼ばれる器具を使い、下から炭火で温めながら
揉んで乾燥させていきます。
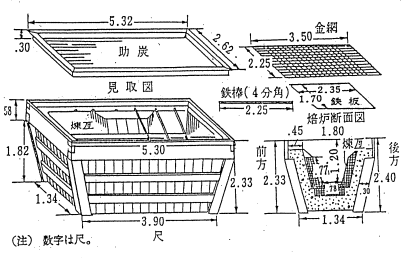

このように手間暇かけてお茶を作っていたのです。
さて、現在はどのようにお茶を作っているのでしょう。
それは次回に、茶工場の中をご案内いたします。

2009年05月19日
山の新茶
しばらくブログをお休みにして、お茶を作っていました。

・・というのは実はウソです。
この写真は契約茶工場でお茶の摘み取り作業の様子です。
この摘採機はそんなに大型ではないのですが、中山間地での茶園で使用するには
適度な大きさです。
ちなみに撮影時期は5月の初旬。茶の芽も、摘むのに適したちょうどいい芽合いです。

さて、この様子を動画で見てみましょう。
こんな感じです。
さて、この後機械で刈った生葉は工場に運ばれますが、ここでトラックに詰め替えです。
生葉をネットの袋に移し替えます。この時人手がかかります。なにせ迅速に仕事を
したいので・・。生葉は鮮度維持が大事なのです。
家族総出で手伝いです。
ここも動画でちょっとだけ見てみましょう。
家族が皆でお茶摘み作業を手伝いする。・・赤ちゃんも含めて。
いいですね。日本の農業の原点を見た。と言ったらいいすぎでしょうか。
さて、この摘んだ生葉は茶工場に運ばれて製茶されます。
次回は茶工場に着いたお茶の葉はどうなるのか、を動画を交えてご紹介します。


・・というのは実はウソです。
この写真は契約茶工場でお茶の摘み取り作業の様子です。
この摘採機はそんなに大型ではないのですが、中山間地での茶園で使用するには
適度な大きさです。
ちなみに撮影時期は5月の初旬。茶の芽も、摘むのに適したちょうどいい芽合いです。

さて、この様子を動画で見てみましょう。
こんな感じです。
さて、この後機械で刈った生葉は工場に運ばれますが、ここでトラックに詰め替えです。
生葉をネットの袋に移し替えます。この時人手がかかります。なにせ迅速に仕事を
したいので・・。生葉は鮮度維持が大事なのです。
家族総出で手伝いです。
ここも動画でちょっとだけ見てみましょう。
家族が皆でお茶摘み作業を手伝いする。・・赤ちゃんも含めて。
いいですね。日本の農業の原点を見た。と言ったらいいすぎでしょうか。
さて、この摘んだ生葉は茶工場に運ばれて製茶されます。
次回は茶工場に着いたお茶の葉はどうなるのか、を動画を交えてご紹介します。





