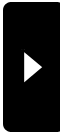2008年10月31日
お茶のことわざ
昔からお茶は朝から飲むとよい、と言われてきました。
これはお茶の中に含まれるカフェインが目を覚まさせ
頭をシャキーンとさせる効果があることを昔の人が
経験から知っていたせいでしょう。

ことわざでも朝茶は三里帰ってでも飲め
ということわざがあります。飲み忘れたら、あとがえってでも飲みなっしぇ
ということです。
ことわざと言えばお茶の子さいさいという
言葉があります。お茶の子というのは、お茶の時に添えて出す
簡単なお菓子のことです。さいさいというのははやし言葉の
一種で俗謡の「のんこさいさい」からきたそうです。
つまり、簡単に食べられるから、簡単に出来ることをいいます。
さらにお茶の子というのは朝飯前に食べる軽食(お団子とか)
なんかもそう呼んだそうです。なぜ朝飯前に軽食を食べるんだ?
と思った人は昔のお百姓さんの苦労を知りませんね。
昔の農家は日の出とともに起き、朝飯前に一仕事をしてたんです。
だから「朝飯前」という言葉もそこから出たのです。
とかなんとか言ってお茶を濁して終わろうと思ったのですが
お茶を濁すの意味も一応押さえときましょう。
これは昔、抹茶を点てる作法をよく知らない者が知ったかぶりをして
アゴをたたいていたら「じゃあやってみろ」となり、実際に抹茶を
点てなければならないはめになっちゃった。狼狽していいかげんな
点てかたをしたら「濁らしているだけじゃないか」と言われて
ショボーン。
そこからその場だけをとりつくろうことを指して言うようになりました。
このブログはお茶を濁しているばかりではないのです。
お茶を濁すこともありますが・・。

なにをむきになってお茶を濁しているんだ。目が血走っているぞ。
奥さんにそんなに怒られたのか?

これはお茶の中に含まれるカフェインが目を覚まさせ
頭をシャキーンとさせる効果があることを昔の人が
経験から知っていたせいでしょう。

ことわざでも朝茶は三里帰ってでも飲め
ということわざがあります。飲み忘れたら、あとがえってでも飲みなっしぇ
ということです。
ことわざと言えばお茶の子さいさいという
言葉があります。お茶の子というのは、お茶の時に添えて出す
簡単なお菓子のことです。さいさいというのははやし言葉の
一種で俗謡の「のんこさいさい」からきたそうです。
つまり、簡単に食べられるから、簡単に出来ることをいいます。
さらにお茶の子というのは朝飯前に食べる軽食(お団子とか)
なんかもそう呼んだそうです。なぜ朝飯前に軽食を食べるんだ?
と思った人は昔のお百姓さんの苦労を知りませんね。
昔の農家は日の出とともに起き、朝飯前に一仕事をしてたんです。
だから「朝飯前」という言葉もそこから出たのです。
とかなんとか言ってお茶を濁して終わろうと思ったのですが
お茶を濁すの意味も一応押さえときましょう。
これは昔、抹茶を点てる作法をよく知らない者が知ったかぶりをして
アゴをたたいていたら「じゃあやってみろ」となり、実際に抹茶を
点てなければならないはめになっちゃった。狼狽していいかげんな
点てかたをしたら「濁らしているだけじゃないか」と言われて
ショボーン。
そこからその場だけをとりつくろうことを指して言うようになりました。
このブログはお茶を濁しているばかりではないのです。
お茶を濁すこともありますが・・。

なにをむきになってお茶を濁しているんだ。目が血走っているぞ。
奥さんにそんなに怒られたのか?

2008年10月30日
お茶の冷蔵
茶店ではお茶をどのように保存しているか知っていらっしゃいますか。
昔は木の茶箱にそのまま入れて保存していました。
冷蔵倉庫などない昔の話しです。
50~60kgはありそうな大きな茶箱をいくつも積み重ねて置くわけです。
そのための倉を作ったりもしました。
下の写真はディスプレイ用の小さな茶箱です。

15年くらい前までは「衣装保管に使うから、古い茶箱ないですか」と
聞かれることもあったのですが、最近はホームセンターなどにある
プラスチックの衣装ケースが軽くて、安くなったので、茶箱を聞かれる
こともなくなりました。
昔の茶箱は内側にブリキが貼ってあり、防湿性にすぐれていました。
しかし、どんなに防湿性がすぐれていると言っても、やはり中には
空気が入っています。酸化があります。お茶にとって酸化は、
味、香りが変わる元なのです。
だから昔のお茶は季節と共に風味が変わってきました。
基本的には古茶臭といって、すねたような臭いに変化していくのですが、
ある時期だけには熟成臭というか、ぷーんと香りたつようになる
時期があるのです。その時期がちょうど夏から秋にかけてでした。
でした、というのは、今はもうそのような保存はしないからです。
今はアルミの包材にいれて、空気を抜いて、ダンボール箱に入れ、
さらにそれを冷蔵倉庫で保存します。
酸化による製品劣化を防ぐためです。
新茶の時の新鮮さを失わないようにです。
基本的には劣化はありませんが、お茶自体に含まれている酸素の影響で
少しの変化はあります。
新茶時に渋かったお茶が年を越して飲んでみると、マイルドに変わる
こともたまにあります。

(これは当店の冷蔵倉庫の中、これは狭いほうです)
マイナス20℃くらいの冷凍で保存する倉庫もあり、そのように保存
されたお茶はまったくと言っていいほど変化しません。

(一度扉を開けたから12℃まであがってしまいました。いつもは8℃くらい)
だから乾燥製品でもあるお茶は、真空パックされた大袋を、さらに
100gとか200g袋に詰め替え、その時点で賞味期限を打ちます。
このように保存技術が進むと品質が良いまま維持できるので、
素晴らしいことには間違いありません。
しかし一つ欠点が・・それは、昔は季節とともに酸化が進み
丸一年目には古茶臭のピークを迎えちょうどその時、新茶の
なんとも言えない新鮮な香りをかぐのです。
新茶のおいしさが本当に身にしみたと思います。
でも新鮮なまま保存できる現代では新茶のインパクトは昔ほどない、
といってもいいでしょう。
一年中均一な品質のお茶が飲める今と、時と共に劣化していくお茶を
飲んでいた昔。でも新茶には真の感動があった昔。
さあ、どっちがいいのでしょう。

うるさいやつは冷凍保存しておくにかぎる。

昔は木の茶箱にそのまま入れて保存していました。
冷蔵倉庫などない昔の話しです。
50~60kgはありそうな大きな茶箱をいくつも積み重ねて置くわけです。
そのための倉を作ったりもしました。
下の写真はディスプレイ用の小さな茶箱です。

15年くらい前までは「衣装保管に使うから、古い茶箱ないですか」と
聞かれることもあったのですが、最近はホームセンターなどにある
プラスチックの衣装ケースが軽くて、安くなったので、茶箱を聞かれる
こともなくなりました。
昔の茶箱は内側にブリキが貼ってあり、防湿性にすぐれていました。
しかし、どんなに防湿性がすぐれていると言っても、やはり中には
空気が入っています。酸化があります。お茶にとって酸化は、
味、香りが変わる元なのです。
だから昔のお茶は季節と共に風味が変わってきました。
基本的には古茶臭といって、すねたような臭いに変化していくのですが、
ある時期だけには熟成臭というか、ぷーんと香りたつようになる
時期があるのです。その時期がちょうど夏から秋にかけてでした。
でした、というのは、今はもうそのような保存はしないからです。
今はアルミの包材にいれて、空気を抜いて、ダンボール箱に入れ、
さらにそれを冷蔵倉庫で保存します。
酸化による製品劣化を防ぐためです。
新茶の時の新鮮さを失わないようにです。
基本的には劣化はありませんが、お茶自体に含まれている酸素の影響で
少しの変化はあります。
新茶時に渋かったお茶が年を越して飲んでみると、マイルドに変わる
こともたまにあります。

(これは当店の冷蔵倉庫の中、これは狭いほうです)
マイナス20℃くらいの冷凍で保存する倉庫もあり、そのように保存
されたお茶はまったくと言っていいほど変化しません。

(一度扉を開けたから12℃まであがってしまいました。いつもは8℃くらい)
だから乾燥製品でもあるお茶は、真空パックされた大袋を、さらに
100gとか200g袋に詰め替え、その時点で賞味期限を打ちます。
このように保存技術が進むと品質が良いまま維持できるので、
素晴らしいことには間違いありません。
しかし一つ欠点が・・それは、昔は季節とともに酸化が進み
丸一年目には古茶臭のピークを迎えちょうどその時、新茶の
なんとも言えない新鮮な香りをかぐのです。
新茶のおいしさが本当に身にしみたと思います。
でも新鮮なまま保存できる現代では新茶のインパクトは昔ほどない、
といってもいいでしょう。
一年中均一な品質のお茶が飲める今と、時と共に劣化していくお茶を
飲んでいた昔。でも新茶には真の感動があった昔。
さあ、どっちがいいのでしょう。

うるさいやつは冷凍保存しておくにかぎる。

2008年10月29日
藤原さんの矢部茶

平成の大合併で色々な自治体がまとまり、大きな市や町になりました。
それはそれで良いことなのでしょうが、昔なじみの町名や村名が
少しずつ使われなくなっていくのは寂しい気もします。
旧上益城郡矢部町は合併により、山都町に変わりました。
矢部という地名はなくなりましたが、「矢部茶」という名前は
残っています。
矢部地方は古くからお茶作りが盛んな地方です。
もともとは釜炒り茶を作る農家が多かったのですが、最近は
玉緑茶(たまりょくちゃ)と呼ばれる蒸し製のお茶が主流に
なっています。
この地方は全般的に標高も割と高く、昼夜の寒暖の差があるので
渋味のはっきりとした味のお茶が作られます。
当店でお付き合いがあるのは旧矢部町の藤原徳門さんです。
藤原さんの茶園はとても管理が行き届いた美しい茶園です。

この藤原さんのお茶はきれいに丸まった形をしており、急須で
出すと濃く出ます。味は甘みと渋味がバランスよくまとまり
お茶本来の味を楽しむことが出来ます。

当店ではこのお茶を「藤原徳門さんの矢部茶」と名前をつけて
販売しております。
矢部茶が飲んでみたい。と思われた時にはいかがでしょうか。

90g入り 980円

2008年10月28日
玉露かりがね
秋の気配が次第に濃くなってきました。
これからだんだんお茶がおいしく感じられる季節になってきます。
新茶の頃のお茶もおいしいけれど、夏を越えて秋の今に時期になり
お茶はさらに熟成されてまろやかさを増します。
今日はこの時期にふさわしい「玉露かりがね」を紹介したいと思います。

かりがねというのは茎のことを言います。
クキが持つ風味ある香りが、玉露の甘みと相まって、独特の味わいを
生み出します。

さて、玉露というのはどんなお茶かご存知でしょうか。
玉露の茶園は普通の煎茶園と違い、摘む20日ほど前からワラで覆い、
日光を遮って育てます。

光を抑えることにより、葉の中のアミノ酸が渋くならず、うま味の
ある状態で摘むことが出来るのです。
この玉露のクキをメインにして作った玉露かりがねのおいしいいれ方を
説明してみたいと思います。
まず、お茶の葉は通常よりやや多目に取り急須に入れます。

お湯を湯飲みで冷まします。温度は約60℃くらい。
お湯の量は少な目がポイントです。

そして温度を下げたお湯を急須に入れ、フタをして約1.5分から2分くらい
待ちます。この待つ時間が大事です。
最後に湯飲みに注ぎますが、複数の湯飲みに注ぐ時はゆっくり交互に
注ぎ分けます。そして最後の一滴まで注ぎ切ることが大事です。

さて、そうやっていれたお茶は格別の味がします。
秋の日のゆったりとした一日にこのようなお茶を一服するのはいかがでしょうか。

玉露かりがね
80g入りで980円

秋の日に一服しながらしみじみ
俺も昔はイケメンでもてたものだ・・と

これからだんだんお茶がおいしく感じられる季節になってきます。
新茶の頃のお茶もおいしいけれど、夏を越えて秋の今に時期になり
お茶はさらに熟成されてまろやかさを増します。
今日はこの時期にふさわしい「玉露かりがね」を紹介したいと思います。

かりがねというのは茎のことを言います。
クキが持つ風味ある香りが、玉露の甘みと相まって、独特の味わいを
生み出します。

さて、玉露というのはどんなお茶かご存知でしょうか。
玉露の茶園は普通の煎茶園と違い、摘む20日ほど前からワラで覆い、
日光を遮って育てます。

光を抑えることにより、葉の中のアミノ酸が渋くならず、うま味の
ある状態で摘むことが出来るのです。
この玉露のクキをメインにして作った玉露かりがねのおいしいいれ方を
説明してみたいと思います。
まず、お茶の葉は通常よりやや多目に取り急須に入れます。

お湯を湯飲みで冷まします。温度は約60℃くらい。
お湯の量は少な目がポイントです。

そして温度を下げたお湯を急須に入れ、フタをして約1.5分から2分くらい
待ちます。この待つ時間が大事です。
最後に湯飲みに注ぎますが、複数の湯飲みに注ぐ時はゆっくり交互に
注ぎ分けます。そして最後の一滴まで注ぎ切ることが大事です。

さて、そうやっていれたお茶は格別の味がします。
秋の日のゆったりとした一日にこのようなお茶を一服するのはいかがでしょうか。

玉露かりがね
80g入りで980円

秋の日に一服しながらしみじみ
俺も昔はイケメンでもてたものだ・・と

2008年10月27日
健軍商店街秋のイベント
健軍商店街、今年の秋のイベントといえば
「健軍・農村地域間交流フェスティバル」です。

これは都市部と農村の交流を深め、お互いに行き来し、特産物の販売
などを通してそれぞれの地域の活性化を図ろうという趣旨のもと
行われるイベントです。その一環として先日の山都町訪問などがありました。
そして今度は健軍商店街でのイベント開催となるのです。
日時は11月22(土)23(日)24(月)の3日間で
ピアクレス(健軍商店街)アーケード内と健軍文化ホールで
行われます。
詳しい内容は11月になってからお知らせするとして、
今日はさわりだけちょっと紹介します。
初日には泉ヶ丘校区の「子供みこし」や城南こばと太鼓クラブ、
それから益城町の広安西小学校音楽部演会などが楽しめます。

16:00からは熊本国府高校軽音楽部演奏会の演奏もあります。

23日は熊本市消防音楽隊の演奏や中沢堅司のミニライブなどもあります。

24日は東野中学校吹奏楽部演奏会。それから3日間通して
琉球國祭り太鼓(エイサー)の演舞が行われます。

そして通りに並ぶのはワゴンセールです。
今回は各商店以外にも熊本国府高校の生徒たちによる模擬店や
「山都町」、「ましきメッセもやい市」の皆さんがワゴンブースで沢山の特産物を
販売します。
盛りだくさんに行われる「健軍・農村地域間交流フェスティバル」
どうぞのぞきに来てみてください。

「健軍・農村地域間交流フェスティバル」です。

これは都市部と農村の交流を深め、お互いに行き来し、特産物の販売
などを通してそれぞれの地域の活性化を図ろうという趣旨のもと
行われるイベントです。その一環として先日の山都町訪問などがありました。
そして今度は健軍商店街でのイベント開催となるのです。
日時は11月22(土)23(日)24(月)の3日間で
ピアクレス(健軍商店街)アーケード内と健軍文化ホールで
行われます。
詳しい内容は11月になってからお知らせするとして、
今日はさわりだけちょっと紹介します。
初日には泉ヶ丘校区の「子供みこし」や城南こばと太鼓クラブ、
それから益城町の広安西小学校音楽部演会などが楽しめます。

16:00からは熊本国府高校軽音楽部演奏会の演奏もあります。

23日は熊本市消防音楽隊の演奏や中沢堅司のミニライブなどもあります。

24日は東野中学校吹奏楽部演奏会。それから3日間通して
琉球國祭り太鼓(エイサー)の演舞が行われます。

そして通りに並ぶのはワゴンセールです。
今回は各商店以外にも熊本国府高校の生徒たちによる模擬店や
「山都町」、「ましきメッセもやい市」の皆さんがワゴンブースで沢山の特産物を
販売します。
盛りだくさんに行われる「健軍・農村地域間交流フェスティバル」
どうぞのぞきに来てみてください。

2008年10月26日
山都町有機農産物フェアー

健軍、農村地域間交流の一環として、山里体験バスツアーが
本日行われました。
これは都市部の住民の方々に山里の農作業体験をしてもらい
併せて有機農産物フェアーに参加してもらおうという試みです。
朝からどんよりとした天気で、雨がふらなければいいが、という
お天気です。
事前の連絡で、午前中に予定していた農作業体験で脱穀作業の経験が
前日の雨の影響で出来なくなり、かわりに山都町ミニ観光をしていただくことになりました。
農作業を期待されていた方には残念なことですが降雨のためと
あれば仕方ありません。

通潤橋の放水を見学した後
鮎の瀬大橋に行くことになりました。

この鮎の瀬大橋は緑川渓谷にかかる吊り橋で、長さ390m
高さ190mの橋です。
この橋の上から見下ろす谷の風景が絶景です。
眺めながら歩いていると、川のほとりにこじんまりと
茶畑が見えます。さすがお茶の里、旧矢部町です。

そうやってしばらく観光の後、お目当ての山都町有機農産物フェアーの会場につきました。
色々な農産物や特産物のコーナーがテントの中に
並べてあります。
おお、ふと見ると、ブログ講座でご一緒している「ほろす」さんの
コーナーではありませんか。
「ほろす」さんのハーブティー、初めて飲ませていただきました。
おっ、この香り。緑茶のおとなしめで、やや単調な香りに比べ
とてもはっきりとしていながらマイルドな香りです。
飲ませていただいたのは矢部茶ブレンド「爽の黄」と「美の赤」の
試飲サンプルです。
お茶とハーブ数種類のブレンド、これはおもしろい香りと味で
とても興味を惹かれました。
お~っと、「ほろす」さんのコーナーの写真を撮るのを忘れちゃった。
いい写真が撮れたかもしれなかったけど、スイマセン。
ハーブティーの写真を置きます。

さて、有機農産物フェアーは少し小雨まじりの中、子供達の太鼓や
高校生のブラスバンド、琉球エイサーなどの出し物を見ながら
進みました。

いくつかのテントで有機農産物や惣菜などが販売され、
有機農産物の書籍なども並べられていました。
山都町は有機農業に意欲的に取り組んでいる町です。
標高の高さも条件としてメリットに働いているのかも知れません。
この利点を生かしてこれからも積極的に進めて、大いに
アピールしていただきたいと思います。

日本の農業は守らなくてはならない。
日本に来た時、稲刈りをやってもらおう。オバマさんに。

2008年10月25日
秋の山茶園
秋も深まりつつある1日、お茶の仕入れを兼ね、山鹿市鹿北にある
茶園の様子を見に行きました。
ここ、鹿北地方は江戸時代からお茶作りの盛んなところで、
良質のお茶が採れます。

中山間地の山あいに茶園を切り開く場合が多く、一つの茶園の面積が
あまり広く取れないので、効率に欠ける部分はありますが、
標高の高さから来るお茶の品質の良さには定評があります。
行ったときにはちょうど秋整枝(あきせいし)が行われているところでした。

秋製枝というのは、春に新芽を摘む時に古い葉を摘み取らないように
今のうちにきれいに形を整えておく作業のことです。
これから寒くなる時期はお茶の木を休ませる期間になります。
ゆっくり十分に休ませると春においしい芽が伸びて来るのです。

このように山あいを縫って茶畑が広がっています。
ここに来ると本当に心がほっと安らぎます。

お茶の倉庫があるところまで下ってきたら、おや、なんだあの雲は!

山の頂上からまるで煙が立ち上っているみたい。いや、天から落ちた
雷のような雲なのか。
この雲、東から西に空を横切って伸びていました。ナンナノダロウ?
それはともかく、ほんの少しでしたが、山里の秋を感じることが
出来たひと時でした。

茶園の様子を見に行きました。
ここ、鹿北地方は江戸時代からお茶作りの盛んなところで、
良質のお茶が採れます。

中山間地の山あいに茶園を切り開く場合が多く、一つの茶園の面積が
あまり広く取れないので、効率に欠ける部分はありますが、
標高の高さから来るお茶の品質の良さには定評があります。
行ったときにはちょうど秋整枝(あきせいし)が行われているところでした。

秋製枝というのは、春に新芽を摘む時に古い葉を摘み取らないように
今のうちにきれいに形を整えておく作業のことです。
これから寒くなる時期はお茶の木を休ませる期間になります。
ゆっくり十分に休ませると春においしい芽が伸びて来るのです。

このように山あいを縫って茶畑が広がっています。
ここに来ると本当に心がほっと安らぎます。

お茶の倉庫があるところまで下ってきたら、おや、なんだあの雲は!

山の頂上からまるで煙が立ち上っているみたい。いや、天から落ちた
雷のような雲なのか。
この雲、東から西に空を横切って伸びていました。ナンナノダロウ?
それはともかく、ほんの少しでしたが、山里の秋を感じることが
出来たひと時でした。

2008年10月24日
お茶の見本市
お茶の流通について
お茶が店頭で売られるまでどのようなルートがあるか
ご存知でしょうか。
1つは産地の茶工場から直接仕入れる方法があります。
当店でも山鹿の茶工場から契約仕入れをしています。
2つ目はJA経済連を通しての入札販売による仕入れです。
これも当店は加盟しております。
ただしこれは茶が採れる時期だけ開かれます。
3つ目は産地問屋さんを通して仕入れる方法。
九州は茶業が盛んなところで、鹿児島、八女、嬉野、宮崎と
各地に問屋さんがあり、それぞれ個性のあるお茶を扱っています。
今回ご紹介するのは、その九州の問屋さんたちが一同に
集まって見本市を開く機会が年に3回ほどあり、その模様です。

行われたのは熊本市内の会館内です。各県の問屋から出品された見本は七百数十点にのぼります。
その中からこれはと思うお茶を選び、参考価格に対して自分の買いたい値段を入れます。参考価格よりも安い場合が多いのですが、
どうしても欲しいお茶の場合、価格が高くなることもあります。


高くなる場合は他の値段より一番高い値段を付けた人が落札です。
安い場合は出典者との協議で決めます。
お茶の外観と香り、そして実際に飲んでみて気に入るかどうか確かめます。

こうしてお茶を選んで仕入れます。
すこしでもおいしいお茶を手に入れて販売するためには色々なルートを持つことも大切です。

お茶の鑑定はスプーンですくって味を見る。
先生、お味はいかが!?

お茶が店頭で売られるまでどのようなルートがあるか
ご存知でしょうか。
1つは産地の茶工場から直接仕入れる方法があります。
当店でも山鹿の茶工場から契約仕入れをしています。
2つ目はJA経済連を通しての入札販売による仕入れです。
これも当店は加盟しております。
ただしこれは茶が採れる時期だけ開かれます。
3つ目は産地問屋さんを通して仕入れる方法。
九州は茶業が盛んなところで、鹿児島、八女、嬉野、宮崎と
各地に問屋さんがあり、それぞれ個性のあるお茶を扱っています。
今回ご紹介するのは、その九州の問屋さんたちが一同に
集まって見本市を開く機会が年に3回ほどあり、その模様です。

行われたのは熊本市内の会館内です。各県の問屋から出品された見本は七百数十点にのぼります。
その中からこれはと思うお茶を選び、参考価格に対して自分の買いたい値段を入れます。参考価格よりも安い場合が多いのですが、
どうしても欲しいお茶の場合、価格が高くなることもあります。


高くなる場合は他の値段より一番高い値段を付けた人が落札です。
安い場合は出典者との協議で決めます。
お茶の外観と香り、そして実際に飲んでみて気に入るかどうか確かめます。

こうしてお茶を選んで仕入れます。
すこしでもおいしいお茶を手に入れて販売するためには色々なルートを持つことも大切です。

お茶の鑑定はスプーンですくって味を見る。
先生、お味はいかが!?

2008年10月23日
ほうじ茶を作るっ
さぁ、今日は「ほうじ茶」作りです!
ナイストライの中学生2人にやってもらうぞー。
我が店の奥からコンパクトな「ほうじ機」をごそごそと
引っ張り出してきます。

これは電気ヒーターで熱しながら、同時にドラムを回転させ
中のお茶の葉を焙じる機械です。
中の温度は90℃~120℃くらいにします。
しばらく熱するとミニ煙突からなにやらモクモクとかすかな煙が
立ち上ってきます。

さぁ、そこへお番茶を入れて、GO!
ナイストライの2人に調整の仕方を教えて、「ほうじ番」をしてもらいます。
なにしろこのほうじ機はちょっと目を離すとすぐ焦げたり、生炒りだったり
するのです。

おや、2人で焙じを調整したりしながら、道行く人達にちゃんと「こんにちは」
と挨拶してるではないか。感心、感心。
ほうじ茶は強く炒るために葉が茶色になるし、出した時のお湯の色も茶色です。
でもとても香ばしい香りがするし、焙じる時にカフェインが蒸気と一緒に
飛ぶために、刺激の少ない、小さいお子さんや高齢者にやさしいお茶に
なります。

さぁ、できたヨ、君達も飲んでごらん。

そう、おいしい!?

何が原因か分からないが
自分を焙じてしまっている。
・・・コメントのしようがない。

ナイストライの中学生2人にやってもらうぞー。
我が店の奥からコンパクトな「ほうじ機」をごそごそと
引っ張り出してきます。

これは電気ヒーターで熱しながら、同時にドラムを回転させ
中のお茶の葉を焙じる機械です。
中の温度は90℃~120℃くらいにします。
しばらく熱するとミニ煙突からなにやらモクモクとかすかな煙が
立ち上ってきます。

さぁ、そこへお番茶を入れて、GO!
ナイストライの2人に調整の仕方を教えて、「ほうじ番」をしてもらいます。
なにしろこのほうじ機はちょっと目を離すとすぐ焦げたり、生炒りだったり
するのです。

おや、2人で焙じを調整したりしながら、道行く人達にちゃんと「こんにちは」
と挨拶してるではないか。感心、感心。
ほうじ茶は強く炒るために葉が茶色になるし、出した時のお湯の色も茶色です。
でもとても香ばしい香りがするし、焙じる時にカフェインが蒸気と一緒に
飛ぶために、刺激の少ない、小さいお子さんや高齢者にやさしいお茶に
なります。

さぁ、できたヨ、君達も飲んでごらん。

そう、おいしい!?

何が原因か分からないが
自分を焙じてしまっている。
・・・コメントのしようがない。

2008年10月22日
ピアクレスキッチン
ピアクレスキッチンをご存知でしょうか。

商店街が空き店舗の有効利用を促進するために行っている事業で
一般の人達が手作りの商品を空店舗を使って販売できる仕組みです。
1日の使用料は1000円。
手軽に利用しやすい料金が受けて何日かおきに継続的に出店する
オーナーも増えてきました。
そしてこのピアクレスキッチンも開始から1周年を迎えました。

今日(22日)の1日オーナーは2人組で出されている「幸ちゃん(さっちゃん)」です。

メニューが前に出してあります。どれどれ。

この「幸ちゃん」の今日のメニューはお弁当とおかず、それと自慢のだご汁です。


それともう一つの売れ筋自慢のロールケーキ、これは午後からの販売です。
それぞれの「一日オーナー」は工夫しながらメニューを研究しています。
また、各々にいつものお得意様がついていらっしゃいます。
10月のこれからのスケジュールです。
来年の3月までは継続決定です。
それ以降も続けていきたいですネ。


ピアクレスキッチンパパ
そう、今のうちに料理を身につけといたほうが・・。


商店街が空き店舗の有効利用を促進するために行っている事業で
一般の人達が手作りの商品を空店舗を使って販売できる仕組みです。
1日の使用料は1000円。
手軽に利用しやすい料金が受けて何日かおきに継続的に出店する
オーナーも増えてきました。
そしてこのピアクレスキッチンも開始から1周年を迎えました。


今日(22日)の1日オーナーは2人組で出されている「幸ちゃん(さっちゃん)」です。

メニューが前に出してあります。どれどれ。

この「幸ちゃん」の今日のメニューはお弁当とおかず、それと自慢のだご汁です。


それともう一つの売れ筋自慢のロールケーキ、これは午後からの販売です。
それぞれの「一日オーナー」は工夫しながらメニューを研究しています。
また、各々にいつものお得意様がついていらっしゃいます。
10月のこれからのスケジュールです。
来年の3月までは継続決定です。
それ以降も続けていきたいですネ。


ピアクレスキッチンパパ
そう、今のうちに料理を身につけといたほうが・・。

2008年10月21日
フレッシュ中学生
今日から中学2年生のナイストライが当店で実習開始です。

今年は9月に引き続き、2校目の受け入れです。
女子2名、さぁ3日間がんばってやってみようネ。
簡単な仕事を少しずつしてもらいます。
こちらは毎日やっている仕事だから特段の感想はないのですが、
中学生達にとっては、やること全部新鮮だったり、緊張したり
するのでしょうね。そしてお客様と接することも新たな体験でしょう。
お店での体験はけっこう彼らの中でずーっと残るのではないかな。
自分達の中学生の頃はナイストライなんてなかったけど、
考えてみたら、自分ちがお店でした。
でも今は店と住居が別々です。みんなそうなってしまってます。
昔は生活と仕事が不可分に結びついていたし、例えサラリーマンの
子供でも、仕事の現場が身近にあったような気がします。
今はそうではないからナイストライの意味があるのかも知れません。


一見経営者に見えるが
じつは「おやじナイストライ」の実習生である。
偉そうにするな!


今年は9月に引き続き、2校目の受け入れです。
女子2名、さぁ3日間がんばってやってみようネ。
簡単な仕事を少しずつしてもらいます。
こちらは毎日やっている仕事だから特段の感想はないのですが、
中学生達にとっては、やること全部新鮮だったり、緊張したり
するのでしょうね。そしてお客様と接することも新たな体験でしょう。
お店での体験はけっこう彼らの中でずーっと残るのではないかな。
自分達の中学生の頃はナイストライなんてなかったけど、
考えてみたら、自分ちがお店でした。
でも今は店と住居が別々です。みんなそうなってしまってます。
昔は生活と仕事が不可分に結びついていたし、例えサラリーマンの
子供でも、仕事の現場が身近にあったような気がします。
今はそうではないからナイストライの意味があるのかも知れません。


一見経営者に見えるが
じつは「おやじナイストライ」の実習生である。
偉そうにするな!

2008年10月20日
お茶を使った石けん
最近お茶を原料にした石けんが、通販で大変な勢いで売れている
そうです。
お茶に含まれる「カテキン」が肌にも有効だということで評判に
なっています。
お茶を原料にした石けんは実は昔からあります。
使われている原料は石けん素材(油脂)とお茶の抽出物。
その他の添加物は出来るだけ使わない方が肌にとっては良いのです。

当店で売っている石けんは「カテキン石けん」
4、5年前から売っています。
作っているのは北九州の「シャボン玉石けん」という会社です。
この会社は創業以来無添加の石けん作りにこだわっています。
お茶石けんなのになぜ緑じゃないの、と思われる方がいるかも
知れません。
お茶の本当の色は茶色なのです。
ではなぜ、飲むお茶はあんなに緑色?それはお湯で出すお茶には
細かい細かい葉の破片が浮いているからです。葉の破片の葉緑素で
あんなに緑に見えるのです。でもそんな緑のお茶も時間が経てば茶色に
変わっていきます。
変わらない緑の素はクロレラなどから抽出した緑色の色素です。
クロレラだって植物だから、使ってもいいんですけどね。
当店のカテキン石けんにはお茶の成分しか入ってないから茶色です。
そして、製造元のシャボン玉石けんも無添加にこだわり続けてこられた
ところです。そこのパンフレットからちょっとだけ抜粋です。




ほんのさわりだけですけど、なんとなく分かっていただけたでしょうか。
このカテキン石けん、余分な化学成分は一切使用していません。
だから使うと、とても自然でつっぱらなく、気持ちが良いのです。
広告宣伝費も乗せていない適正価格 1個 735円です。

中年以降になると若い時以上に清潔に気をつけるべきだ。
加齢臭の臭いを競い合っていてはいけない。

そうです。
お茶に含まれる「カテキン」が肌にも有効だということで評判に
なっています。
お茶を原料にした石けんは実は昔からあります。
使われている原料は石けん素材(油脂)とお茶の抽出物。
その他の添加物は出来るだけ使わない方が肌にとっては良いのです。

当店で売っている石けんは「カテキン石けん」
4、5年前から売っています。
作っているのは北九州の「シャボン玉石けん」という会社です。
この会社は創業以来無添加の石けん作りにこだわっています。
お茶石けんなのになぜ緑じゃないの、と思われる方がいるかも
知れません。
お茶の本当の色は茶色なのです。
ではなぜ、飲むお茶はあんなに緑色?それはお湯で出すお茶には
細かい細かい葉の破片が浮いているからです。葉の破片の葉緑素で
あんなに緑に見えるのです。でもそんな緑のお茶も時間が経てば茶色に
変わっていきます。
変わらない緑の素はクロレラなどから抽出した緑色の色素です。
クロレラだって植物だから、使ってもいいんですけどね。
当店のカテキン石けんにはお茶の成分しか入ってないから茶色です。
そして、製造元のシャボン玉石けんも無添加にこだわり続けてこられた
ところです。そこのパンフレットからちょっとだけ抜粋です。




ほんのさわりだけですけど、なんとなく分かっていただけたでしょうか。
このカテキン石けん、余分な化学成分は一切使用していません。
だから使うと、とても自然でつっぱらなく、気持ちが良いのです。
広告宣伝費も乗せていない適正価格 1個 735円です。

中年以降になると若い時以上に清潔に気をつけるべきだ。
加齢臭の臭いを競い合っていてはいけない。

2008年10月19日
もう年末の準備
10月の半ばを過ぎたのに、昼間は暑いですね。
なんだか時が逆戻りしている感じですが、ちゃんと月日は過ぎています。
早くも今年の年末に向けての「茶袋」のデザインを選ばなくては
なりません。早いですね~。

来年は丑年(うしどし)です。
十二支を全部言えますか?
子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
干支というのは本来十二支と十干が組み合わさったものだそうです。
十干は 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸 からなるものです。
干支の組み合わせは60通りあるそうで、
来年はその中の26番目の己丑(つちのとうし)だそうです。
さぁ、来年はいい年になってくれるかな。

今から牛の着ぐるみを試着して、
一体正月に何をしようというのだ。

なんだか時が逆戻りしている感じですが、ちゃんと月日は過ぎています。
早くも今年の年末に向けての「茶袋」のデザインを選ばなくては
なりません。早いですね~。

来年は丑年(うしどし)です。
十二支を全部言えますか?
子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
干支というのは本来十二支と十干が組み合わさったものだそうです。
十干は 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸 からなるものです。
干支の組み合わせは60通りあるそうで、
来年はその中の26番目の己丑(つちのとうし)だそうです。
さぁ、来年はいい年になってくれるかな。

今から牛の着ぐるみを試着して、
一体正月に何をしようというのだ。

2008年10月18日
ある土曜日の健軍商店街
健軍商店街
今日18日は朝の清掃の日です。
今回は一般のお客様のボランティアも募集して行います。
参加されたお客様には「健軍カード」100ポイントを差し上げます。
朝の8時集合で、約1時間の朝の清掃です。

アーケードの中や駐車場などを皆で手分けして掃除いたしました。
11時からは健軍カードの交換会が行われました。
ぴあスタンプの時から今まで毎月1回、すでに150回以上行われてきた
交換会ですが、今回は初めての試みとして、満点カードに刻印される
番号を指定した交換会です。

今日の交換会では130枚ほどのカードを交換いたしました。

終わればもう12時です。
お隣の「まちの駅」でお弁当でも買って
いただきま~す。


健軍版レレレのおじさん
(オリジナルとだいぶ違うな~)

今日18日は朝の清掃の日です。
今回は一般のお客様のボランティアも募集して行います。
参加されたお客様には「健軍カード」100ポイントを差し上げます。
朝の8時集合で、約1時間の朝の清掃です。

アーケードの中や駐車場などを皆で手分けして掃除いたしました。
11時からは健軍カードの交換会が行われました。
ぴあスタンプの時から今まで毎月1回、すでに150回以上行われてきた
交換会ですが、今回は初めての試みとして、満点カードに刻印される
番号を指定した交換会です。

今日の交換会では130枚ほどのカードを交換いたしました。

終わればもう12時です。
お隣の「まちの駅」でお弁当でも買って
いただきま~す。


健軍版レレレのおじさん
(オリジナルとだいぶ違うな~)

2008年10月17日
バンチャについて。
「バンチャ」ってどんなお茶かご存知ですか。
普通は番茶と書きます。
一般的には最初のお茶を摘み取った後に伸びてくる
固く大きくなった葉で作ったお茶で、下級茶の総称として
使われることが多いようです。最初に摘むお茶を1番茶といい、
その後の2番茶、3番茶を使用することから、番茶と呼ばれる
ようです。夏の日差しをたくさん浴びて、ざっくり大きめの
葉っぱで、やや渋めのお茶です。
もう一つは晩茶と記述すべきお茶があります。
これは、日本各地に伝わる土着のお茶のことで、様々な種類が
あります。晩茶の晩は、遅いなどの意味があり、
1番茶を遅く摘んで作るのですが、土着のお茶だけあり、
私たちが通常目にしない意表をつく姿かたちのお茶があります。


この茶色の異様なお茶は富山県の朝日町(旧名)で作られる
「バタバタ茶」と呼ばれるお茶です。
バタバタとはいかにも面白い名前です。これはその飲み方に
関係があるようです。
このお茶は煮出した後に、大き目の茶せん
(竹の先の細かく切れ目を入れたもの)
で泡立てて飲むお茶なのです。その泡立てる様子がせかせかと
あわただしい様子なのでこの名前が付いたそうです。
そしてこのお茶の大きな特色は中国で飲まれる黒茶(プーアル茶などの
後発酵茶)と同じ仲間で、乳酸発酵をさせています。
プーアール茶といえば、一時期ダイエットにも良いといわれたお茶。
このバタバタ茶はかなり古くからあり、煎茶よりもずっと歴史があります。
一説によると縄文時代に中国から伝わったとも言われています。
とてもユニークなこのお茶、少々酸味があり、普通のお茶とは
まったく違う味ですが、ユニークゆえに注目もされ、最近は缶入り
ドリンクも出たそうです。

普通じゃない、面白晩茶、
このバタバタ茶だけではないのです。 また次に紹介します。

バタバタとしてるようだが、
実はのどかな秋の一日

普通は番茶と書きます。
一般的には最初のお茶を摘み取った後に伸びてくる
固く大きくなった葉で作ったお茶で、下級茶の総称として
使われることが多いようです。最初に摘むお茶を1番茶といい、
その後の2番茶、3番茶を使用することから、番茶と呼ばれる
ようです。夏の日差しをたくさん浴びて、ざっくり大きめの
葉っぱで、やや渋めのお茶です。
もう一つは晩茶と記述すべきお茶があります。
これは、日本各地に伝わる土着のお茶のことで、様々な種類が
あります。晩茶の晩は、遅いなどの意味があり、
1番茶を遅く摘んで作るのですが、土着のお茶だけあり、
私たちが通常目にしない意表をつく姿かたちのお茶があります。


この茶色の異様なお茶は富山県の朝日町(旧名)で作られる
「バタバタ茶」と呼ばれるお茶です。
バタバタとはいかにも面白い名前です。これはその飲み方に
関係があるようです。
このお茶は煮出した後に、大き目の茶せん
(竹の先の細かく切れ目を入れたもの)
で泡立てて飲むお茶なのです。その泡立てる様子がせかせかと
あわただしい様子なのでこの名前が付いたそうです。
そしてこのお茶の大きな特色は中国で飲まれる黒茶(プーアル茶などの
後発酵茶)と同じ仲間で、乳酸発酵をさせています。
プーアール茶といえば、一時期ダイエットにも良いといわれたお茶。
このバタバタ茶はかなり古くからあり、煎茶よりもずっと歴史があります。
一説によると縄文時代に中国から伝わったとも言われています。
とてもユニークなこのお茶、少々酸味があり、普通のお茶とは
まったく違う味ですが、ユニークゆえに注目もされ、最近は缶入り
ドリンクも出たそうです。

普通じゃない、面白晩茶、
このバタバタ茶だけではないのです。 また次に紹介します。

バタバタとしてるようだが、
実はのどかな秋の一日

2008年10月16日
ゴマ太鼓
「大家さ~ん、いるか~い」
「なんだよ、よたろうじゃないか、どうしたんだ手に何か持って」
「大家さん、こんなものもらったんだけど、これなにか聞こうかと思って」

「どれど~れ、おやこれはゴマ太鼓っちゅうお菓子でないかい」
「これ、ゴマ太鼓って言うの?なんだか胡麻がべっとりくっついてて、
気持ちが悪いんだけど・・。」
「これは胡麻を水飴などで固めたお菓子で、肥後の黒胡麻太鼓と
肥後の白胡麻太鼓っうお菓子だよ。うめいんだよ」
「そうか、それなら安心した。食ってみよ~と、
・・・ポリッ、うん、これはいける」

「これよたろう、おねえばっかり食ってねえで、わしにも食わせろ」
「ポリッ、ポリポリ」

「あ~あ、よたろう、一人でぱくぱく食ってしまってるじゃないか」
「あ、これは中にアーモンドも入ってるんだ、おや大豆もへえってる」

「あ~あ、とうとう食ってしまいやがった、やい、その残りの白胡麻太鼓、よこせ」
「おや、大家さんの頭の上にとまっているのは、ハチじゃあないのかい」
「なに、蜂が止まっているだと~?おっとっとそりゃたいへんだ」
「あ~っ、あっち逃げてった!おいこら~捕まえてやる!」
「おーい、よたろう、どこへ追っかけていくんだ~。
あーあ、行っちまいやがった。・・とうとう胡麻かされてしまっちまった」
(^_^;)
おちゃいち山陽堂で販売しております。
1個105円です。

「なんだよ、よたろうじゃないか、どうしたんだ手に何か持って」
「大家さん、こんなものもらったんだけど、これなにか聞こうかと思って」

「どれど~れ、おやこれはゴマ太鼓っちゅうお菓子でないかい」
「これ、ゴマ太鼓って言うの?なんだか胡麻がべっとりくっついてて、
気持ちが悪いんだけど・・。」
「これは胡麻を水飴などで固めたお菓子で、肥後の黒胡麻太鼓と
肥後の白胡麻太鼓っうお菓子だよ。うめいんだよ」
「そうか、それなら安心した。食ってみよ~と、
・・・ポリッ、うん、これはいける」

「これよたろう、おねえばっかり食ってねえで、わしにも食わせろ」
「ポリッ、ポリポリ」

「あ~あ、よたろう、一人でぱくぱく食ってしまってるじゃないか」
「あ、これは中にアーモンドも入ってるんだ、おや大豆もへえってる」

「あ~あ、とうとう食ってしまいやがった、やい、その残りの白胡麻太鼓、よこせ」
「おや、大家さんの頭の上にとまっているのは、ハチじゃあないのかい」
「なに、蜂が止まっているだと~?おっとっとそりゃたいへんだ」
「あ~っ、あっち逃げてった!おいこら~捕まえてやる!」
「おーい、よたろう、どこへ追っかけていくんだ~。
あーあ、行っちまいやがった。・・とうとう胡麻かされてしまっちまった」
(^_^;)
おちゃいち山陽堂で販売しております。
1個105円です。

2008年10月15日
茶缶くん
お茶缶です。

食卓上では地味な存在かもしれません。
和紙貼り缶が多く使われています。
桜の皮を身にまとったシャレ者もいます。
中はステンレス製で機密性を高めるために二重フタになっています。

お茶にとっては、空気に触れ合うことが一番大敵です。
まず、空気中の湿気を吸い取って、自身がしけってしまいます。
そして、酸素に触れて酸化を起こします。
これは食品全般に言えることですが、長い期間空気中に置いておくと
臭いが悪くなり、味も落ちてきます。
だから、なるべく空気をシャットアウトしたほうがいいのです。
お茶の品質を守るためがんばってきた「茶缶」くん。
最近はチャック式袋の増加で、活躍の場が減っています。

近頃キャンディボックスに使えそうなお茶缶も出てきました。



食卓上では地味な存在かもしれません。
和紙貼り缶が多く使われています。
桜の皮を身にまとったシャレ者もいます。
中はステンレス製で機密性を高めるために二重フタになっています。

お茶にとっては、空気に触れ合うことが一番大敵です。
まず、空気中の湿気を吸い取って、自身がしけってしまいます。
そして、酸素に触れて酸化を起こします。
これは食品全般に言えることですが、長い期間空気中に置いておくと
臭いが悪くなり、味も落ちてきます。
だから、なるべく空気をシャットアウトしたほうがいいのです。
お茶の品質を守るためがんばってきた「茶缶」くん。
最近はチャック式袋の増加で、活躍の場が減っています。

近頃キャンディボックスに使えそうなお茶缶も出てきました。


2008年10月14日
どくだみ茶を飲んでみる
世の中には色々な種類の健康茶があります。
それらの健康茶は昔から人々に飲まれ、人間の健康に寄与してきました。

それらに一つずつスポットを当て、紹介していきたいと思います。
それぞれの健康茶が体のどんなところに有効に働くか、一番知りたい
ところですよね。 が、しかし、薬事法というものがあって、
あんなとこに効く、こんなものに効くなどということは、
薬以外は言ってはいけない。となっております。
ダイエットに効くなどと言った日には、「証拠を見せろ」とばかりに
その筋からの警告文が来るそうで・・。
さてそこで、それならば、次に人が知りたいであろう、
「そのお茶はどんな味なのか?苦いのか、まずいのか?」ということを
わたくしが皆様に代わって身をもって飲んでリポートしてみたいと
思います。
第1弾は「どくだみ茶」
体に良さそうだ、ということは聞いてるが、にがいのではないか?
と、皆さん思われているのではないでしょうか。
さっそく飲んでみました。

まず、これが、どくだみ茶です。
皆さんご存知の庭の片隅などに自生している、あの草です。
独特のにおいがあり、その臭いのせいで、昔はドクダメ(毒溜め)
と呼ばれ、そこからドクダミという名前になったという説があるくらいです。
ただし、その薬効は定評があり、なんにでも効き目があるから
「十薬」という漢方名もあります。
さて、飲んでみましょう。
まず、一つかみポットに入れます。

お湯をそそぎます。
10分ほど待っていると、茶色の汁が出てきます。

グラスに入れてみると、琥珀色のけっこうきれいな色にでます。
コレハバーボンデスヨ。セイブゲキミタイニイッキニノンデミテヨ。

まず、香りをかいでみます。
十分焙煎されているはずだが、生のどくだみの香りがまだわずかに
残っています。ちょっとムッとする臭い・・。
一口飲んでみると、
・・・。
これを飲んで気づいたこと。味は香りによって半分以上決まる。
生のどくだみの臭いがそのまま味に反映される感じです。
これは渋味ではない、苦味でもない。
もし、臭いがなかったら、案外あっさりと飲める味ではないでしょうか。
もちろん生のどくだみほどの臭いの強さはありませんし、
飲みなれたら、意外に気にならないのでは、という気もします。
納豆のほうがよっぽど強い臭いです。
効果効能について興味を持たれたら、インターネットで検索すると
色々どんどん出てきます。
一番目に付くのはデトックス効果かな。
まあそういうわけで、どくだみを飲んでみた結論は、
どくだみは臭いに慣れさえすれば、十分飲める!
どくだみをどくだみたらしめているのは
この臭いだ!
ちなみに当店ではこのどくだみ茶
100g入りで315円で販売しております。

ティーバッグタイプもあります。

それらの健康茶は昔から人々に飲まれ、人間の健康に寄与してきました。

それらに一つずつスポットを当て、紹介していきたいと思います。
それぞれの健康茶が体のどんなところに有効に働くか、一番知りたい
ところですよね。 が、しかし、薬事法というものがあって、
あんなとこに効く、こんなものに効くなどということは、
薬以外は言ってはいけない。となっております。
ダイエットに効くなどと言った日には、「証拠を見せろ」とばかりに
その筋からの警告文が来るそうで・・。
さてそこで、それならば、次に人が知りたいであろう、
「そのお茶はどんな味なのか?苦いのか、まずいのか?」ということを
わたくしが皆様に代わって身をもって飲んでリポートしてみたいと
思います。
第1弾は「どくだみ茶」
体に良さそうだ、ということは聞いてるが、にがいのではないか?
と、皆さん思われているのではないでしょうか。
さっそく飲んでみました。

まず、これが、どくだみ茶です。
皆さんご存知の庭の片隅などに自生している、あの草です。
独特のにおいがあり、その臭いのせいで、昔はドクダメ(毒溜め)
と呼ばれ、そこからドクダミという名前になったという説があるくらいです。
ただし、その薬効は定評があり、なんにでも効き目があるから
「十薬」という漢方名もあります。
さて、飲んでみましょう。
まず、一つかみポットに入れます。

お湯をそそぎます。
10分ほど待っていると、茶色の汁が出てきます。

グラスに入れてみると、琥珀色のけっこうきれいな色にでます。
コレハバーボンデスヨ。セイブゲキミタイニイッキニノンデミテヨ。

まず、香りをかいでみます。
十分焙煎されているはずだが、生のどくだみの香りがまだわずかに
残っています。ちょっとムッとする臭い・・。
一口飲んでみると、
・・・。
これを飲んで気づいたこと。味は香りによって半分以上決まる。
生のどくだみの臭いがそのまま味に反映される感じです。
これは渋味ではない、苦味でもない。
もし、臭いがなかったら、案外あっさりと飲める味ではないでしょうか。
もちろん生のどくだみほどの臭いの強さはありませんし、
飲みなれたら、意外に気にならないのでは、という気もします。
納豆のほうがよっぽど強い臭いです。
効果効能について興味を持たれたら、インターネットで検索すると
色々どんどん出てきます。
一番目に付くのはデトックス効果かな。
まあそういうわけで、どくだみを飲んでみた結論は、
どくだみは臭いに慣れさえすれば、十分飲める!
どくだみをどくだみたらしめているのは
この臭いだ!
ちなみに当店ではこのどくだみ茶
100g入りで315円で販売しております。

ティーバッグタイプもあります。

2008年10月13日
とうがらし梅茶
カプサイシンって知っていますか?
これはトウガラシに含まれる辛味成分で、
対内に吸収されたカプサイシンは脳内に運ばれて
内臓感覚神経に働き、副腎のアドレナリンの働きを活発に
して、発汗作用があります。
そんなカプサイシンを手軽においしく飲めるのがこれ
「とうがらし梅茶」です。

紀州の梅肉と北海道の真昆布を使った梅昆布茶をベースに
とうがらしのピリッとした辛さを加えたぴりから昆布茶です。


飲んでみると頭がピピっと発汗しますよ!?
1杯分ずつの個包装で24袋入りで630円です。

罰ゲームでとうがらしを食べる前はおとなしい男だが
↓
↓
↓
↓

これは人が変わる。

これはトウガラシに含まれる辛味成分で、
対内に吸収されたカプサイシンは脳内に運ばれて
内臓感覚神経に働き、副腎のアドレナリンの働きを活発に
して、発汗作用があります。
そんなカプサイシンを手軽においしく飲めるのがこれ
「とうがらし梅茶」です。

紀州の梅肉と北海道の真昆布を使った梅昆布茶をベースに
とうがらしのピリッとした辛さを加えたぴりから昆布茶です。


飲んでみると頭がピピっと発汗しますよ!?
1杯分ずつの個包装で24袋入りで630円です。

罰ゲームでとうがらしを食べる前はおとなしい男だが
↓
↓
↓
↓

これは人が変わる。

2008年10月12日
小さな大納言
当店で地道ながらコツコツと売れ続けているお菓子があります。
商品名は「花かずら」いわゆる「きんつば」というお菓子です。

この「きんつば」の由来を調べてみると、名前は刀の鍔(つば)から
来ているようです。
江戸時代に京都で作られ始められたらしく、もともとは丸型で、
実際に刀の鍔の模様入りもあります。
四角の形をしているものは「角きんつば」と呼ばれるそうです。

最初はその色から「銀つば」と呼ばれていたらしいのですが、
製法が江戸に渡った時に「銀より金の方が景気がよい」という理由で
「金つば」に変わったそうです。
きんつばの方が呼びやすいということもあったのでしょうね。
いくつか製法のバリエーションはあるようで、当店のきんつばは
大納言小豆を寒天と水飴で固め、周囲を砂糖で固めてあります。
さて、原料に使われている、この大納言小豆。
これまたどんなものかと調べてみると、あらぬ方向に興味が向かって
しまいました。
大納言小豆と普通の小豆は違うらしいのです。
小豆も大納言も同じくマメ科ササゲ属に属しているのですが、
大納言の品種には、あかね大納言、ホクト大納言、カムイ大納言、
トヨミ、丹波等多くの種類があり、
毎年品種改良が繰り返されているのです。
つまり大納言と小豆は品種が違う、ということ。
内容がどう違うかというと、
大納言種の特徴は、まずその皮の風味にあり、外皮自体の味が
濃厚で小豆独特の味があり、小豆に比べて煮崩れしにくく、
炊き上げると香りの良い餡が出来るそうです。大納言は豆皮が
柔らかく仕上がり、皮と餡とのバランスが食感を損ねることがなく、
粒餡や鹿の子豆に適した種であるということです。
対して小豆種は、こし餡に適した豆であり、その粒子は
大納言種よりも比較的細かいけれど、外皮は大納言種よりも堅く
煮くずれしやすく味も薄いとのこと。
また中味の粒子の滑らかさは大納言種よりも優れているので
口当たりの点で漉し餡に適しているとのことです。
どのように違うのかは分かりましたが、なぜ、大納言と言うのか?
私の疑問はそちらに向かいました。
大納言と言うようになったわけは「腹を割らないやつ」だからだそう・・。
つまり、煮立てても皮がはじけない、ということでしょうか。
上の説明でも、煮崩れしにくい、とありました。でもなぜ大納言?
大納言というのは宮中の官位の名前で、とても高い位です。
大納言になると殿中で刀を抜いても切腹しなくていい、
というくらい高位らしいです。
歴史的に有名な事件としては忠臣蔵の浅野内匠頭の抜刀事件が
あります。その内匠頭(たくみのかみ)という位は「従五位上」という
正式名称だったそう。
大納言というのは「正三位」という官位で、
本来は公家しか就けなかった位ですが江戸幕府のときには
尾張徳川家と紀州徳川家、駿府徳川家しか就くことのできない
非常な高位だったのですね。
それで、浅野内匠頭は殿中で抜刀して切腹になりましたが、
もし、大納言だったら切腹しなくてもよかった? というわけです。
大納言小豆は偉いヤツ?
ついでに言うと大納言の下に中納言というのがあって、
官位でいうと「従三位」。有名なのは水戸徳川家の徳川光圀。
従三位の唐名は「黄門侍郎」というそうで、そこから水戸黄門という
名前が付いたそうです。天下の副将軍は中納言で、大納言より
一つ下だった。殿中で刀振り回したら、切腹もありなのか・・。
話しはあらぬ方向に向かい、このままだと収拾がつかなくなるので、止めますが、

つまり、「花かずら」というきんつばは、大納言小豆を使ったおいしいお菓子
ということを言いたかったのです。

京都で作っています。 1個 105円です。

よせ、そんなにまでして、腹を割って話したくない。
顔もこわいし。

商品名は「花かずら」いわゆる「きんつば」というお菓子です。

この「きんつば」の由来を調べてみると、名前は刀の鍔(つば)から
来ているようです。
江戸時代に京都で作られ始められたらしく、もともとは丸型で、
実際に刀の鍔の模様入りもあります。
四角の形をしているものは「角きんつば」と呼ばれるそうです。

最初はその色から「銀つば」と呼ばれていたらしいのですが、
製法が江戸に渡った時に「銀より金の方が景気がよい」という理由で
「金つば」に変わったそうです。
きんつばの方が呼びやすいということもあったのでしょうね。
いくつか製法のバリエーションはあるようで、当店のきんつばは
大納言小豆を寒天と水飴で固め、周囲を砂糖で固めてあります。
さて、原料に使われている、この大納言小豆。
これまたどんなものかと調べてみると、あらぬ方向に興味が向かって
しまいました。
大納言小豆と普通の小豆は違うらしいのです。
小豆も大納言も同じくマメ科ササゲ属に属しているのですが、
大納言の品種には、あかね大納言、ホクト大納言、カムイ大納言、
トヨミ、丹波等多くの種類があり、
毎年品種改良が繰り返されているのです。
つまり大納言と小豆は品種が違う、ということ。
内容がどう違うかというと、
大納言種の特徴は、まずその皮の風味にあり、外皮自体の味が
濃厚で小豆独特の味があり、小豆に比べて煮崩れしにくく、
炊き上げると香りの良い餡が出来るそうです。大納言は豆皮が
柔らかく仕上がり、皮と餡とのバランスが食感を損ねることがなく、
粒餡や鹿の子豆に適した種であるということです。
対して小豆種は、こし餡に適した豆であり、その粒子は
大納言種よりも比較的細かいけれど、外皮は大納言種よりも堅く
煮くずれしやすく味も薄いとのこと。
また中味の粒子の滑らかさは大納言種よりも優れているので
口当たりの点で漉し餡に適しているとのことです。
どのように違うのかは分かりましたが、なぜ、大納言と言うのか?
私の疑問はそちらに向かいました。
大納言と言うようになったわけは「腹を割らないやつ」だからだそう・・。
つまり、煮立てても皮がはじけない、ということでしょうか。
上の説明でも、煮崩れしにくい、とありました。でもなぜ大納言?
大納言というのは宮中の官位の名前で、とても高い位です。
大納言になると殿中で刀を抜いても切腹しなくていい、
というくらい高位らしいです。
歴史的に有名な事件としては忠臣蔵の浅野内匠頭の抜刀事件が
あります。その内匠頭(たくみのかみ)という位は「従五位上」という
正式名称だったそう。
大納言というのは「正三位」という官位で、
本来は公家しか就けなかった位ですが江戸幕府のときには
尾張徳川家と紀州徳川家、駿府徳川家しか就くことのできない
非常な高位だったのですね。
それで、浅野内匠頭は殿中で抜刀して切腹になりましたが、
もし、大納言だったら切腹しなくてもよかった? というわけです。
大納言小豆は偉いヤツ?
ついでに言うと大納言の下に中納言というのがあって、
官位でいうと「従三位」。有名なのは水戸徳川家の徳川光圀。
従三位の唐名は「黄門侍郎」というそうで、そこから水戸黄門という
名前が付いたそうです。天下の副将軍は中納言で、大納言より
一つ下だった。殿中で刀振り回したら、切腹もありなのか・・。
話しはあらぬ方向に向かい、このままだと収拾がつかなくなるので、止めますが、

つまり、「花かずら」というきんつばは、大納言小豆を使ったおいしいお菓子
ということを言いたかったのです。

京都で作っています。 1個 105円です。

よせ、そんなにまでして、腹を割って話したくない。
顔もこわいし。