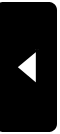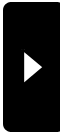2008年12月10日
手もみ茶の作り方
お茶を作る工場を見たことはおありでしょうか。
大きな機械が沢山並んでいます。

この中をお茶の葉が通りながら、蒸されたり、揉まれたり、
乾燥させられていって、やっと製品としてのお茶が出来上がります。
でも昔はどうやってお茶を作っていたのでしょう。
こんな機械がないむかし・・。
江戸時代から明治にかけては、手で揉んでお茶を作っていました。
さあ、どんな具合に作っていたのでしょう。
数年前に私たちが行った手揉み茶研修会の写真をもとに
ご説明いたしましょう。
まず最初は摘んできたお茶の葉を蒸します。
当時は「せいろ」で蒸していました。

「せいろ」に生葉(摘んできた茶の葉)を平らに入れ、蒸気の
良く出る「こしき」の上に乗せ、ふたをします。まもなくふたの
隙間から蒸気が出始めるので、手早く茶葉をまぜ、
再びふたをします。香気の変化に気を付けて青臭みが無くなり、
甘涼しい香りが出始めたら、冷却台に移し、急冷します。
蒸し時間は蒸気の発生状態、茶葉の硬さ、投入量の
違いなどで一定ではありませんが、30~40秒程度です。
次に「焙炉」(ほいろ)と呼ばれるものに火を起こします。
「焙炉」というのは下から熱を当てながら上で揉みながら乾燥させる
道具です。これは揉む人の身体に大きさが合い、終始平均した
温度が長時間保てるように作ります。木枠に板を張りその内側を
赤粘土やしっくいで固め、中央部にはレンガを使うこともあります。

これは最初に新聞紙やまきで種火を起こしているところ。

これは「助炭」(じょたん)と呼ばれるもので、和紙で作ってあり、
これを焙炉の上にかぶせます。「かけご」とも呼びます。
種火が起こったら木炭を入れます。

木炭の量は1日分で約5kgです。うちわで扇いで火をまんべんなく広げます。

木炭が赤くなってきたら、上からわら(ころも藁)を均等にかぶせます。

わらが燃えて黒くなりました。このわらは発熱を均等にするために敷きます。
梁にする鉄棒を7本斜めに渡します。

次に金網(やや網目の幅の広い)を敷きます。


助炭を上に乗せます。これは、和紙を幾重にも張り合わせたものです。
のりには小麦粉を使います。

蒸しておいた茶葉を広げます。今回は蒸し葉3kgで作ります。

露切り(葉ぶるい)です。揉みやすくするため水分を蒸発させる操作です。
蒸し葉を小手に拾い、軽く指先を動かし、助炭の全面に茶葉が
広がるように、高さ約40cmのところから振るい落とします。乾くに従い
拾う量を多くし、振るい落とす位置を低くします。

回転もみ(ころがし):茶葉を集散、力を加え、水分の蒸発を促し
ながら茶葉の組織、細胞を破壊し、柔らかにする操作です。
回転揉みはもむ力の程度を基準に3つの操作に分けます。
始め小手で早く揉むのが「軽回転揉み」。大手にし、力を強くかける
のを「重回転揉み」茶葉を練るようにし、もっとも強い力を加える最後
の操作を「練り揉み」と呼びます。

玉解き、中上げ: 玉解きは回転揉みの最終段階で出来る茶の固まりを
ほぐす操作です。少しづつ力を減らし横揉みで解きます。
中上げは茶を中火かごに移し、平らに広げて置き、その間に
茶葉の各部の水分量を均一にする操作です。所要時間、約10分。
中揉み:もみ切りで茶によれ形をつける操作で、はじめは小手で
3手ぐらいに茶を軽く拾い、手早に振り、「もみ切り」をします。乾くに
従い、6拾い程度の大手にし、葉をそろえることに注意し、手使い位置
を低くして力を加えます。操作の末期には「でんぐり揉み」を併用します。
「でんぐり揉み」とは茶を助炭の中央に集め、両手で茶をおさえ、
その手に交互に押し手と受け手を受け持たせ、茶に回転を与える
手使いをいいます。
「もみ切り」は茶を両手で挟み、小指と食指とを締めて茶を掌の中心から
もみ散らすように、手の平を前後に激しくすり合わせます。
手使い位置が助炭に近づいた時は、いわゆる「拝みもみ」にし、力を入れ、
散らすのを控えめにして茶を揃え、力を加え、茶の水分の圧出をします。

仕上げもみ: 茶の形を整え、香味を良くする操作です。
方法には「もみ切り仕上げ」「こくりもみ仕上げ」「板ずり仕上げ」
などがありますが、その中で広く使われているのが「こくりもみ仕上げ」
です。要領は茶を両手で強く押さえ、指先を合わせて右の指先を
助炭につけ、茶を握る気持ちで受け手の指を曲げたり伸ばしたりして、
茶に回転を与えます。形、および色が整い、茶が手からすべり出る
ようになればOKです。
乾燥: 同一助炭でもよいが、あらかじめ用意しておいた70℃前後の
助炭上に茶を薄く広げて乾燥させます。焦げ香がつかないように注意します。

さあ!これで完成です!
この工程を全部こなすのに約3時間ほどかかります!
大変な肉体労働といっていいでしょう。
しかしお茶の味を決めるのは揉み次第なので、気が抜けません。
今は機械がやってくれますが、昔のお茶は貴重でありがたかった
というのもわかるような気がします。

手もみ名人が大汗をかいて揉んだお茶は
塩味が効いて、とてもおいしい。

大きな機械が沢山並んでいます。

この中をお茶の葉が通りながら、蒸されたり、揉まれたり、
乾燥させられていって、やっと製品としてのお茶が出来上がります。
でも昔はどうやってお茶を作っていたのでしょう。
こんな機械がないむかし・・。
江戸時代から明治にかけては、手で揉んでお茶を作っていました。
さあ、どんな具合に作っていたのでしょう。
数年前に私たちが行った手揉み茶研修会の写真をもとに
ご説明いたしましょう。
まず最初は摘んできたお茶の葉を蒸します。
当時は「せいろ」で蒸していました。

「せいろ」に生葉(摘んできた茶の葉)を平らに入れ、蒸気の
良く出る「こしき」の上に乗せ、ふたをします。まもなくふたの
隙間から蒸気が出始めるので、手早く茶葉をまぜ、
再びふたをします。香気の変化に気を付けて青臭みが無くなり、
甘涼しい香りが出始めたら、冷却台に移し、急冷します。
蒸し時間は蒸気の発生状態、茶葉の硬さ、投入量の
違いなどで一定ではありませんが、30~40秒程度です。
次に「焙炉」(ほいろ)と呼ばれるものに火を起こします。
「焙炉」というのは下から熱を当てながら上で揉みながら乾燥させる
道具です。これは揉む人の身体に大きさが合い、終始平均した
温度が長時間保てるように作ります。木枠に板を張りその内側を
赤粘土やしっくいで固め、中央部にはレンガを使うこともあります。

これは最初に新聞紙やまきで種火を起こしているところ。

これは「助炭」(じょたん)と呼ばれるもので、和紙で作ってあり、
これを焙炉の上にかぶせます。「かけご」とも呼びます。
種火が起こったら木炭を入れます。

木炭の量は1日分で約5kgです。うちわで扇いで火をまんべんなく広げます。

木炭が赤くなってきたら、上からわら(ころも藁)を均等にかぶせます。

わらが燃えて黒くなりました。このわらは発熱を均等にするために敷きます。
梁にする鉄棒を7本斜めに渡します。

次に金網(やや網目の幅の広い)を敷きます。


助炭を上に乗せます。これは、和紙を幾重にも張り合わせたものです。
のりには小麦粉を使います。

蒸しておいた茶葉を広げます。今回は蒸し葉3kgで作ります。

露切り(葉ぶるい)です。揉みやすくするため水分を蒸発させる操作です。
蒸し葉を小手に拾い、軽く指先を動かし、助炭の全面に茶葉が
広がるように、高さ約40cmのところから振るい落とします。乾くに従い
拾う量を多くし、振るい落とす位置を低くします。

回転もみ(ころがし):茶葉を集散、力を加え、水分の蒸発を促し
ながら茶葉の組織、細胞を破壊し、柔らかにする操作です。
回転揉みはもむ力の程度を基準に3つの操作に分けます。
始め小手で早く揉むのが「軽回転揉み」。大手にし、力を強くかける
のを「重回転揉み」茶葉を練るようにし、もっとも強い力を加える最後
の操作を「練り揉み」と呼びます。

玉解き、中上げ: 玉解きは回転揉みの最終段階で出来る茶の固まりを
ほぐす操作です。少しづつ力を減らし横揉みで解きます。
中上げは茶を中火かごに移し、平らに広げて置き、その間に
茶葉の各部の水分量を均一にする操作です。所要時間、約10分。
中揉み:もみ切りで茶によれ形をつける操作で、はじめは小手で
3手ぐらいに茶を軽く拾い、手早に振り、「もみ切り」をします。乾くに
従い、6拾い程度の大手にし、葉をそろえることに注意し、手使い位置
を低くして力を加えます。操作の末期には「でんぐり揉み」を併用します。
「でんぐり揉み」とは茶を助炭の中央に集め、両手で茶をおさえ、
その手に交互に押し手と受け手を受け持たせ、茶に回転を与える
手使いをいいます。
「もみ切り」は茶を両手で挟み、小指と食指とを締めて茶を掌の中心から
もみ散らすように、手の平を前後に激しくすり合わせます。
手使い位置が助炭に近づいた時は、いわゆる「拝みもみ」にし、力を入れ、
散らすのを控えめにして茶を揃え、力を加え、茶の水分の圧出をします。

仕上げもみ: 茶の形を整え、香味を良くする操作です。
方法には「もみ切り仕上げ」「こくりもみ仕上げ」「板ずり仕上げ」
などがありますが、その中で広く使われているのが「こくりもみ仕上げ」
です。要領は茶を両手で強く押さえ、指先を合わせて右の指先を
助炭につけ、茶を握る気持ちで受け手の指を曲げたり伸ばしたりして、
茶に回転を与えます。形、および色が整い、茶が手からすべり出る
ようになればOKです。
乾燥: 同一助炭でもよいが、あらかじめ用意しておいた70℃前後の
助炭上に茶を薄く広げて乾燥させます。焦げ香がつかないように注意します。

さあ!これで完成です!
この工程を全部こなすのに約3時間ほどかかります!
大変な肉体労働といっていいでしょう。
しかしお茶の味を決めるのは揉み次第なので、気が抜けません。
今は機械がやってくれますが、昔のお茶は貴重でありがたかった
というのもわかるような気がします。

手もみ名人が大汗をかいて揉んだお茶は
塩味が効いて、とてもおいしい。

2008年12月06日
お茶の仕入れ先2
お茶の流通にはいくつかの方法があります。
一番単純なのが生産者が直接販売する方法。
実際にやっておられますし、それなりに売り上げている方も
いらっしゃいます。
中間マージンがいらないから、いいのではないかとも思われる
のですが、そう簡単にはいかない場合も多いようです。
理由は一つには、小売販売のノウハウは結構複雑で難しいこと。
販売なら販売に専心する部分がないと中々簡単には売れません。
もう一つはお茶の場合は品質のばらつきがけっこうあり、
年間を通して均一で高品質なお茶を提供するには「合組」(ごうぐみ)
といわれるブレンドがどうしても必要なことが挙げられます。
合組についてはまたいつかお話しするとして、
つまりお茶の流通では基本的に「①生産」「②流通仲介1(JA)」
「③流通仲介2(問屋)」「④販売(小売)」という4つがあります。
①が直接④をやる場合もあるし、③と④が一緒の場合もあります。
当店の場合、④の小売業です。
仕入は①からも②からも③からも仕入れます。
単純にどこから仕入れた方がいいものを手に入れられるかということは
一慨に言えません。それぞれにいいものがあるからです。
そんなわけで昨日、JA熊本経済連の仕入れに行ってまいりました。
経済連の入札場です。この日は今年最後の入札で、点数も少ないので
お願いして写真に入っていただきました。

入札はほとんどの場合、新茶時期(4~5月)二番茶以降の時期(6~8月)
に行われます。
県内北から南まで、鹿北から水俣までのお茶が出てきます。

また、値段を付け合う入札方式なので、自分が付けた値段で落ちる、落ちない
があり駆け引きの面白さもあります。
JA経済連入札のバリエーションの一つに品評会があり、こちらも
全国品評会、九州品評会とあります。
これは2年前の鹿児島で行われた品評会に行った時の写真です。

にやけたカメラ目線がなんとも目ざわりですが、
こうして色々なお茶に出会う努力をしています(?)

一番単純なのが生産者が直接販売する方法。
実際にやっておられますし、それなりに売り上げている方も
いらっしゃいます。
中間マージンがいらないから、いいのではないかとも思われる
のですが、そう簡単にはいかない場合も多いようです。
理由は一つには、小売販売のノウハウは結構複雑で難しいこと。
販売なら販売に専心する部分がないと中々簡単には売れません。
もう一つはお茶の場合は品質のばらつきがけっこうあり、
年間を通して均一で高品質なお茶を提供するには「合組」(ごうぐみ)
といわれるブレンドがどうしても必要なことが挙げられます。
合組についてはまたいつかお話しするとして、
つまりお茶の流通では基本的に「①生産」「②流通仲介1(JA)」
「③流通仲介2(問屋)」「④販売(小売)」という4つがあります。
①が直接④をやる場合もあるし、③と④が一緒の場合もあります。
当店の場合、④の小売業です。
仕入は①からも②からも③からも仕入れます。
単純にどこから仕入れた方がいいものを手に入れられるかということは
一慨に言えません。それぞれにいいものがあるからです。
そんなわけで昨日、JA熊本経済連の仕入れに行ってまいりました。
経済連の入札場です。この日は今年最後の入札で、点数も少ないので
お願いして写真に入っていただきました。

入札はほとんどの場合、新茶時期(4~5月)二番茶以降の時期(6~8月)
に行われます。
県内北から南まで、鹿北から水俣までのお茶が出てきます。

また、値段を付け合う入札方式なので、自分が付けた値段で落ちる、落ちない
があり駆け引きの面白さもあります。
JA経済連入札のバリエーションの一つに品評会があり、こちらも
全国品評会、九州品評会とあります。
これは2年前の鹿児島で行われた品評会に行った時の写真です。

にやけたカメラ目線がなんとも目ざわりですが、
こうして色々なお茶に出会う努力をしています(?)

2008年12月04日
お茶の仕入先1
今日はお茶の仕入れで山鹿市の「岳間製茶」へ行ってまいりました。

ここ岳間というのは、旧鹿本郡鹿北町にあり、合併後山鹿市になりました。
昔から茶業の盛んなところで、江戸時代には細川公に献上するお茶も
作っていました。

福岡県との北の県境なのですが、一山越えて北に行けば八女地方という、
なるほどお茶作りに関しては適地なのだということがよく分かります。
鹿北には岳間以外にも茶工場はいくつかありますが、
その中でも「岳間製茶」はトップクラスの生産量を誇ります。
こちらは倉庫の建物

こちらが工場です。奥の方に続いています。

店内は広々としており、農産物販売所も併設しています。

これは別の側面を見たところ。お茶を冷蔵保管する冷蔵庫も完備。

近くには岳間渓谷キャンプ場もあり、夏場は観光客でにぎわいます。
とにかく自然に恵まれたところで、空気も街中と違います。
そんなところで作られたお茶は当店のメインの味なのです。

岳間製茶の地図



ここ岳間というのは、旧鹿本郡鹿北町にあり、合併後山鹿市になりました。
昔から茶業の盛んなところで、江戸時代には細川公に献上するお茶も
作っていました。

福岡県との北の県境なのですが、一山越えて北に行けば八女地方という、
なるほどお茶作りに関しては適地なのだということがよく分かります。
鹿北には岳間以外にも茶工場はいくつかありますが、
その中でも「岳間製茶」はトップクラスの生産量を誇ります。
こちらは倉庫の建物

こちらが工場です。奥の方に続いています。

店内は広々としており、農産物販売所も併設しています。

これは別の側面を見たところ。お茶を冷蔵保管する冷蔵庫も完備。

近くには岳間渓谷キャンプ場もあり、夏場は観光客でにぎわいます。
とにかく自然に恵まれたところで、空気も街中と違います。
そんなところで作られたお茶は当店のメインの味なのです。

岳間製茶の地図


2008年12月02日
予防はうがいから
寒い時期になってきました。
今年の12月は寒くなりそうだという予報です。
風邪など引かぬよう注意しなければなりません。
特に今年は新型インフルエンザがまん延するかもしれない
というこわい情報もあります。
インフルエンザウィルスに「取りつかれない」ためにはいくつか
注意すべきポイントがあるそうです。
1、ウィルスは日光に弱い
太陽の光に弱く、短時間日光を当てるだけで死滅すると
言われています。晴れの日には衣類をまめに日に当てると良い
そうです。
2、湿度を保つ
ウィルスが活発化するのは低温、低湿度の時だそうです。
部屋の温度も60%くらいに保っておいたほうが良いとのこと。
カラカラ空気は要注意ですね。
3、部屋の換気はまめに
汚れた空気はひとの気管や粘膜をいためます。
傷ついた粘膜からウィルスが入りこみやすいので部屋の空気は
新鮮なものにしましょう。
4、予防にはうがいを
さて、ウィルスをなるべく体の中に入れないようにすることも重要です。
そのためにはうがいが効果的。
ただ、うがいだけでは100%シャットアウトは無理です。
でも入りこんでしまったウィルスにも有効なのがお茶のうがい。
お茶に含まれるカテキンがウィルスの突起にくっついて、
ウィルスの細胞への侵入を邪魔します。
これは私の体験上よく効きますので、ぜひお試しを。
原理を図解すると下のようになります。




ウィルスのスパイクにカテキンがくっつくと細胞に取り付きにくくなる
というわけです。
なにごとも予防が一番。

今年の12月は寒くなりそうだという予報です。
風邪など引かぬよう注意しなければなりません。
特に今年は新型インフルエンザがまん延するかもしれない
というこわい情報もあります。
インフルエンザウィルスに「取りつかれない」ためにはいくつか
注意すべきポイントがあるそうです。
1、ウィルスは日光に弱い
太陽の光に弱く、短時間日光を当てるだけで死滅すると
言われています。晴れの日には衣類をまめに日に当てると良い
そうです。
2、湿度を保つ
ウィルスが活発化するのは低温、低湿度の時だそうです。
部屋の温度も60%くらいに保っておいたほうが良いとのこと。
カラカラ空気は要注意ですね。
3、部屋の換気はまめに
汚れた空気はひとの気管や粘膜をいためます。
傷ついた粘膜からウィルスが入りこみやすいので部屋の空気は
新鮮なものにしましょう。
4、予防にはうがいを
さて、ウィルスをなるべく体の中に入れないようにすることも重要です。
そのためにはうがいが効果的。
ただ、うがいだけでは100%シャットアウトは無理です。
でも入りこんでしまったウィルスにも有効なのがお茶のうがい。
お茶に含まれるカテキンがウィルスの突起にくっついて、
ウィルスの細胞への侵入を邪魔します。
これは私の体験上よく効きますので、ぜひお試しを。
原理を図解すると下のようになります。




ウィルスのスパイクにカテキンがくっつくと細胞に取り付きにくくなる
というわけです。
なにごとも予防が一番。

2008年11月27日
茶柱を立てるぞー 2
さて、なぜ「週刊山崎くん」の撮影クルーが
茶柱の立つお茶はありませんか?
と尋ねてきたか、ということです。

実は、実は、
「宝くじを当てるためには?」
という大きな(?)テーマがあったのです。
レポーターの山内要さんと丸井純子さんが、宝くじを当てる秘訣(?)を
街に出てレポートしていたのです。
それで、どこから引っ掛けたか、「茶柱が立つと良い事がある」という
言い伝えを確認し、実践しようと、お茶屋である当店まで来られたと
いうことらしいのです。
事情は分かりました。
でも・・・、茶柱は簡単には・・立たないのです・・よ。
そこで取り出したお茶は、茎のたくさん入った「白折」(しらおれ)と呼ばれる
お茶と「玉露かりがね」という、これまた玉露の茎がたくさん入ったお茶。
この中から茎を選りだしてどうだ、どうだ、とお湯に浮かべてみたが、
あきません。みな茎が平行に浮かんでしまいます。

さあ、どうしたらいいのでしょう。
前回述べたように片方に重しを付ければ良いとは思うのですが
これという決め手がありません。
レポーターおよびスタッフの皆さんと話していると、山内要さんが
とにかく茎をたくさん出せばいくつか立つのではないかと言われ、
丸井純子さんが、普通の急須で出ないのなら、湯冷ましで
茎ごと出したらいかが、と重要な解決策を申されました。
そこで、このような茎のいっぱい入っているお茶を

湯冷ましに入れ、お湯をどばっと注ぐ。

これを、湯飲みに注ぐと・・、
たくさ~ん茎が湯飲みに出てきます。
それを、よーく見てみると・・。
出たー!
立ってるやつがいるー!

そう、たくさん出せば中に立つやつも出てきたのです。
そうか、とにかく数打ちゃ当たる、てことか・・。
こんなに茎が多いとあんまり飲む気はしないけど。
縁起をかつぐならこのいれ方だね。
これできっと宝くじもバッチリ当たる(?)
この「週刊山崎くん」宝くじレポートの巻は12月11日の放映だそうです。
茶柱のところはカットされたりして・・・。

茶柱が大きいと、かなう夢も大きいのかな?

茶柱の立つお茶はありませんか?
と尋ねてきたか、ということです。

実は、実は、
「宝くじを当てるためには?」
という大きな(?)テーマがあったのです。
レポーターの山内要さんと丸井純子さんが、宝くじを当てる秘訣(?)を
街に出てレポートしていたのです。
それで、どこから引っ掛けたか、「茶柱が立つと良い事がある」という
言い伝えを確認し、実践しようと、お茶屋である当店まで来られたと
いうことらしいのです。
事情は分かりました。
でも・・・、茶柱は簡単には・・立たないのです・・よ。
そこで取り出したお茶は、茎のたくさん入った「白折」(しらおれ)と呼ばれる
お茶と「玉露かりがね」という、これまた玉露の茎がたくさん入ったお茶。
この中から茎を選りだしてどうだ、どうだ、とお湯に浮かべてみたが、
あきません。みな茎が平行に浮かんでしまいます。

さあ、どうしたらいいのでしょう。
前回述べたように片方に重しを付ければ良いとは思うのですが
これという決め手がありません。
レポーターおよびスタッフの皆さんと話していると、山内要さんが
とにかく茎をたくさん出せばいくつか立つのではないかと言われ、
丸井純子さんが、普通の急須で出ないのなら、湯冷ましで
茎ごと出したらいかが、と重要な解決策を申されました。
そこで、このような茎のいっぱい入っているお茶を

湯冷ましに入れ、お湯をどばっと注ぐ。

これを、湯飲みに注ぐと・・、
たくさ~ん茎が湯飲みに出てきます。
それを、よーく見てみると・・。
出たー!
立ってるやつがいるー!

そう、たくさん出せば中に立つやつも出てきたのです。
そうか、とにかく数打ちゃ当たる、てことか・・。
こんなに茎が多いとあんまり飲む気はしないけど。
縁起をかつぐならこのいれ方だね。
これできっと宝くじもバッチリ当たる(?)
この「週刊山崎くん」宝くじレポートの巻は12月11日の放映だそうです。
茶柱のところはカットされたりして・・・。

茶柱が大きいと、かなう夢も大きいのかな?

2008年11月26日
茶柱を立てるぞーッ
「茶柱の立つお茶はありませんか?」
こんなことを聞かれる前から実は気にしてはいたのです。
茶柱を立てる方法を・・。
「茶柱」というのは茶の茎、もしくは葉軸、専門家は「棒」とか呼んだり
しています。この茎がお湯の中で垂直に立っている状態を言います。

現在飲まれているお茶はまったくといっていいほど茶柱が立ちません。
それは茎が湯飲みの中に流れ出ることがないからです。
理由は急須にあります。今は多くの急須には、不要な茎や粉が出ない
ようにアミが貼ってあるのです。

シャットアウトされた茎は湯飲みの中に出ようがないのです。
仮に出たとしても簡単には立ちません。
普通の茎はお湯に浮かべると平行に浮いてしまいます。

それでは立ち上がる茎はどんなものでしょうか。
上級茶の茎は横一文字のへしゃげた断面になっており、肥料の
効いていない茶や遅く摘んだ番茶などは断面が丸太のような丸い
形をしています。茶柱が立ちやすいのは丸太棒の方、安物の茶です。
茎の両端で比重が違うと、重い方が下になり、釣り針のうきのように
縦に浮かぶというわけです。
でもそう簡単に両端で比重の違う茎があるわけではありません。
(と思っていました)
じゃあ、茎の片方になにか重いものをくっつけてみたらどうだろう。
このような発想は、ものごとを極めようとする人間にとって自然な発想
です。
色々と試してみました。片方にご飯つぶをくっつけてみたり、他のもので
試したりと・・でも中々うまいぐあいに立ってくれません。
そもそも何で茶柱を立てたいのだ?
そう、素朴な疑問。
これは茶柱が立つと縁起がいいのです。
これは吉事の前兆として、昔から言われています。
茶柱が立つことにより身を立て出世する。家の大黒柱が立つ。などの
語呂合わせから来ているそうです。 それで・・
これは今日現実にあったことなのですが、
突然当店になんの前触れもなく現れたテレビクルー。
お茶の話題でも、商店街の話題でもなさそう・・。
何で「週刊山崎くん」の撮影クルーが茶柱が立つお茶を探しているのだ?
真相は明日に続きます。

こんなことを聞かれる前から実は気にしてはいたのです。
茶柱を立てる方法を・・。
「茶柱」というのは茶の茎、もしくは葉軸、専門家は「棒」とか呼んだり
しています。この茎がお湯の中で垂直に立っている状態を言います。

現在飲まれているお茶はまったくといっていいほど茶柱が立ちません。
それは茎が湯飲みの中に流れ出ることがないからです。
理由は急須にあります。今は多くの急須には、不要な茎や粉が出ない
ようにアミが貼ってあるのです。

シャットアウトされた茎は湯飲みの中に出ようがないのです。
仮に出たとしても簡単には立ちません。
普通の茎はお湯に浮かべると平行に浮いてしまいます。

それでは立ち上がる茎はどんなものでしょうか。
上級茶の茎は横一文字のへしゃげた断面になっており、肥料の
効いていない茶や遅く摘んだ番茶などは断面が丸太のような丸い
形をしています。茶柱が立ちやすいのは丸太棒の方、安物の茶です。
茎の両端で比重が違うと、重い方が下になり、釣り針のうきのように
縦に浮かぶというわけです。
でもそう簡単に両端で比重の違う茎があるわけではありません。
(と思っていました)
じゃあ、茎の片方になにか重いものをくっつけてみたらどうだろう。
このような発想は、ものごとを極めようとする人間にとって自然な発想
です。
色々と試してみました。片方にご飯つぶをくっつけてみたり、他のもので
試したりと・・でも中々うまいぐあいに立ってくれません。
そもそも何で茶柱を立てたいのだ?
そう、素朴な疑問。
これは茶柱が立つと縁起がいいのです。
これは吉事の前兆として、昔から言われています。
茶柱が立つことにより身を立て出世する。家の大黒柱が立つ。などの
語呂合わせから来ているそうです。 それで・・
これは今日現実にあったことなのですが、
突然当店になんの前触れもなく現れたテレビクルー。
お茶の話題でも、商店街の話題でもなさそう・・。
何で「週刊山崎くん」の撮影クルーが茶柱が立つお茶を探しているのだ?
真相は明日に続きます。

2008年11月21日
お茶の香り
お茶の香りというとどのような香りを思い浮かべますか。
香ばしくあまい香り?新鮮な青葉の香り?

お茶の香りを作る要素はいくつもあり、複雑です。
お茶を作る最後の工程で乾燥を進め、香ばしさを付けるために
熱を加えることを火入れといいます。
この火入れを強くするか弱くするかで、お茶の香ばしさが変わって
きます。また、火入れのやり方もいくつかあります。
大きなドラムの中で熱風を吹き付けながら乾燥させるやり方。
上から遠赤外線を当てながらお茶をその下に流す方法。など。
当店で行っているやり方は遠赤外線で乾燥させる方法です。
この火入れを行うとお茶の葉の中でピラジン類という成分が増え、
香ばしさが増します。
ただし、新茶の時期は火入れを抑えます。それはお茶本来の新鮮な
香りを楽しんでもらうためです。
この新茶の香りは揮発性のアルコールやエステルから生まれる
もので、量が少ないのと、揮発性のために長続きせずに消えて
しまいます。
だから新茶の新鮮な香りはその時だけの貴重な香りということも
言えます。
また、ウーロン茶などの中国茶も多彩な香りを持ちます。
ウーロン茶などは、葉を酸化させて作るので香りの成分も変化
しているのです。酸化の度合いで香りが変わり、そのため色々な
香りがあります。
日本茶でも最近は品種の違いで香りに個性を出そうと試みられて
います。
お茶の香りのバリエーションを増やすことはこれから期待されている
分野でもあり、楽しみな分野でもあります。

この人のダンスは華麗だが、香りは加齢(臭)だ

香ばしくあまい香り?新鮮な青葉の香り?

お茶の香りを作る要素はいくつもあり、複雑です。
お茶を作る最後の工程で乾燥を進め、香ばしさを付けるために
熱を加えることを火入れといいます。
この火入れを強くするか弱くするかで、お茶の香ばしさが変わって
きます。また、火入れのやり方もいくつかあります。
大きなドラムの中で熱風を吹き付けながら乾燥させるやり方。
上から遠赤外線を当てながらお茶をその下に流す方法。など。
当店で行っているやり方は遠赤外線で乾燥させる方法です。
この火入れを行うとお茶の葉の中でピラジン類という成分が増え、
香ばしさが増します。
ただし、新茶の時期は火入れを抑えます。それはお茶本来の新鮮な
香りを楽しんでもらうためです。
この新茶の香りは揮発性のアルコールやエステルから生まれる
もので、量が少ないのと、揮発性のために長続きせずに消えて
しまいます。
だから新茶の新鮮な香りはその時だけの貴重な香りということも
言えます。
また、ウーロン茶などの中国茶も多彩な香りを持ちます。
ウーロン茶などは、葉を酸化させて作るので香りの成分も変化
しているのです。酸化の度合いで香りが変わり、そのため色々な
香りがあります。
日本茶でも最近は品種の違いで香りに個性を出そうと試みられて
います。
お茶の香りのバリエーションを増やすことはこれから期待されている
分野でもあり、楽しみな分野でもあります。

この人のダンスは華麗だが、香りは加齢(臭)だ

2008年11月13日
結納
九州で「お茶を入れる」と言うと特別な意味があります。
それは「結納する」という意味です。「茶をする」とも言います。

結納にお茶を使うのは日本では九州独特の風習のようです。
九州以外の府県では結納にはお茶は入れません。
それでは結納に茶を使うのはどういう意味があるのでしょう。
昔はお茶は食と密接な関係がありました。
場合によっては茶と米や雑穀などを一緒に煮たりもしました。
そして、その食事を作るのは一家の主婦の重要な役目です。
その大事な主婦になる人を迎え入れたいという思いを込めて
茶を贈る風習になったのであろうと言われています。
また、通常お茶は葬儀の際の返礼など法事に良く使われます。
これはお茶が仏教伝来とともに日本に伝わり、お坊さんによって
広まっていったからだと考えられます。
そして、お寺で飲むために墓地の横などに茶の木が植えられて
いたことも多いようです。
そこで、九州以外の地方ではお茶をお祝いや内祝として贈るのは
避けられる傾向があるのですが、九州では結納にお茶を使う関係
からか、お祝いなどでも良く使われます。
さて、結納のお茶は目録に書かれる時、どのような字で書かれるでしょう。
「葉茶」と書いたり「御知家」と書いたりします。御知家というのは
当て字ですね。
結納には当て字はとても多くて、「目録」を「茂久録」と書いたり、
「昆布」を「子生婦」とか、「するめ」を「寿留女」とか書きます。
お酒のことは「家内喜多留」(やなぎだる)とか言います。別の読み方
すれば、「かないきたる」ですね。
まあ、そんな結納ですが、中に入れるお茶は通常、あまり高いお茶は
使いません。なぜかと言うと、
「良いお茶はよく出る」
いったん結婚して家に嫁いだら、簡単に(家を)出るな。
よく出ては困る。という意味があるそうです。面白いですね。
そのような意味のある結納ですが、最近は簡単に済ませたいと言う
傾向が強くなりました。仲人さんも立てることが非常に少なくなり、
婚約、結納という儀式も最近はだいぶ様変わりしつつあります。

(永久の誓いはほんとうに永久に賞味期限が続くのか、
それが問題だ。)

それは「結納する」という意味です。「茶をする」とも言います。

結納にお茶を使うのは日本では九州独特の風習のようです。
九州以外の府県では結納にはお茶は入れません。
それでは結納に茶を使うのはどういう意味があるのでしょう。
昔はお茶は食と密接な関係がありました。
場合によっては茶と米や雑穀などを一緒に煮たりもしました。
そして、その食事を作るのは一家の主婦の重要な役目です。
その大事な主婦になる人を迎え入れたいという思いを込めて
茶を贈る風習になったのであろうと言われています。
また、通常お茶は葬儀の際の返礼など法事に良く使われます。
これはお茶が仏教伝来とともに日本に伝わり、お坊さんによって
広まっていったからだと考えられます。
そして、お寺で飲むために墓地の横などに茶の木が植えられて
いたことも多いようです。
そこで、九州以外の地方ではお茶をお祝いや内祝として贈るのは
避けられる傾向があるのですが、九州では結納にお茶を使う関係
からか、お祝いなどでも良く使われます。
さて、結納のお茶は目録に書かれる時、どのような字で書かれるでしょう。
「葉茶」と書いたり「御知家」と書いたりします。御知家というのは
当て字ですね。
結納には当て字はとても多くて、「目録」を「茂久録」と書いたり、
「昆布」を「子生婦」とか、「するめ」を「寿留女」とか書きます。
お酒のことは「家内喜多留」(やなぎだる)とか言います。別の読み方
すれば、「かないきたる」ですね。
まあ、そんな結納ですが、中に入れるお茶は通常、あまり高いお茶は
使いません。なぜかと言うと、
「良いお茶はよく出る」
いったん結婚して家に嫁いだら、簡単に(家を)出るな。
よく出ては困る。という意味があるそうです。面白いですね。
そのような意味のある結納ですが、最近は簡単に済ませたいと言う
傾向が強くなりました。仲人さんも立てることが非常に少なくなり、
婚約、結納という儀式も最近はだいぶ様変わりしつつあります。

(永久の誓いはほんとうに永久に賞味期限が続くのか、
それが問題だ。)

2008年11月12日
日々是好日

日々是好日
自分は「ヒビコレコウジツ」と読んでいました。
毎日を良き日だと受けとめて過ごすことだと思っていました。
でもこれは本当は「ニチニチコレコウニチ」と読むらしいのです。
昔中国の「雲門」という禅宗のお坊さんが言った言葉だそうで、
その日一日をただありのままに生きる楚々とした境地のこと。
禅独特の奥の深い思想で、
とても簡単に言ってしまえば、
この一瞬を大事にして行きよ。
ということらしいです。
そうか、それってホント大事ですよね。
でも普段あまり意識することがない。
だから、この言葉を時折思い出して、意識せよ。という
ことなのでしょう。
実はその「好日」という言葉を名前にさせて頂いたお茶が
出来ました。
牛に引かれて善光寺まいりをモチーフにした絵と共にデザイン
してあります。
このお茶を飲んで、ゆっくりと今生きていることをかみしめる。
とそこまでは、大げさに考えなくてもよろしいですが、
ホッと一息入れて見たいときにいかがでしょう。

1袋 1050円

この人は“日々是口実”

2008年11月10日
茶園の見張り番
茶園の上に立つ、これは何でしょう?

答えはセンプウキです。
そう扇風機。高い柱の上から風を送ります。
でも何のために扇風機があるのでしょう。
それは春先の霜を予防するためです。
高いところにある空気は地面の近くよりも
温度が高いから上空のやや高い気温の空気を
下に吹きやって霜が葉につくのを防ぎます。
だからこの扇風機の名前は防霜ファンと言います。

これが動くのは新芽が出てから。
一年のほとんどはぼーっと何もせずに立ったままです。

(この写真は春先の八女の茶園です)

何もしないでぼーっとしてるとたまには暴走したくなる。「暴走ファン」
疲れた時にはゆっくりお茶でもどうぞ・・。


答えはセンプウキです。
そう扇風機。高い柱の上から風を送ります。
でも何のために扇風機があるのでしょう。
それは春先の霜を予防するためです。
高いところにある空気は地面の近くよりも
温度が高いから上空のやや高い気温の空気を
下に吹きやって霜が葉につくのを防ぎます。
だからこの扇風機の名前は防霜ファンと言います。

これが動くのは新芽が出てから。
一年のほとんどはぼーっと何もせずに立ったままです。

(この写真は春先の八女の茶園です)

何もしないでぼーっとしてるとたまには暴走したくなる。「暴走ファン」
疲れた時にはゆっくりお茶でもどうぞ・・。

2008年11月03日
釜炒り茶
釜炒り茶・・・聞いたことはある名前だと思います。
文字通り釜で炒って作ったお茶です。
お茶を作るには、最初に釜で炒るか蒸気で蒸すかして、お茶の酵素の
働きを止めます。これを専門用語で「殺青」と言います。
釜炒り茶はこの殺青を釜で行ったお茶のことで、昔は熊本市近郊でも
農家の庭先などで、自家用に釜炒り茶を作っていました。

昔は上の写真のように手で炒って作りましたが、今は「炒り葉機」という
機械で炒り、揉みと乾燥も機械でします。
全国的に見れば、現在作られているお茶の99%は蒸気で蒸して作る煎茶
などのお茶になってしまっており、釜炒り茶は希少なお茶になってしまいました。
なぜ希少なお茶になったかというと、釜炒り茶が持っている商品特性が、
今の消費者が求める価値感に合わなくなってしまったから、と言うしか
ありません。
具体的には、出した時のお湯の色が黄色っぽく、薄いということがあります。お茶を飲む時にはその色も重要な評価の要素になります。

それから、味の薄さもあります。蒸気で蒸したお茶は熱のため
比較的中まで細胞膜が破壊されており、そのため内部のアミノ酸などの
成分が出てきやすくなっています。
またお湯の色も緑が濃くなります。釜炒り茶はその反対なわけです。
しかし良い点もあります。香りが良く、あっさりした味であることです。
釜で炒った独特の釜香(かまか)があります。
また、一部で釜炒り茶を見直そうという動きもあります。

先日行われました全国お茶まつり熊本大会の中でも「釜炒り茶フォーラム」
という形で討論会が行われました。
釜炒り茶フォーラムの報告はこちら→●
釜炒り茶は九州で、特に多く作られています。
熊本県の山都町から宮崎県の五ヶ瀬にいたる地方と天草地方、それと
佐賀県の嬉野が産地として有名です。
一説によると15世紀ごろに渡来した中国人によって九州地方に
釜炒り製法が伝わったといわれていますし、それ以前に釜で炒って作る
お茶があったともいわれています。
そのような釜炒り茶は色々な課題をかかえながらも一部の生産家たちに
よって作り続けられています。
当店では私が、釜炒り茶の香りと、煎茶の色、味をともに生かしたお茶を
作ろうと考えました。そしてブレンドにより両方の長所を生かして
「かおりっ子」というお茶を作りました。

「かおりっ子」100g 525円
本当は釜炒りだけのお茶を出したいのですが、総合評価でどうしても
落ちるので、売れ残ってしまいます。
もっと香りに特徴のある釜炒り茶がほしい~。
と思っているのです。
(追伸)
釜炒り茶については価値を認めて、広めたいという気持ちは大いにあるの
ですが、現実の製品とのギャップがあります。それだけ製造が難しいという
こともあるかも知れませんが、もどかしさもあります。

釜入家ファミリー。
シャイな一家である。

文字通り釜で炒って作ったお茶です。
お茶を作るには、最初に釜で炒るか蒸気で蒸すかして、お茶の酵素の
働きを止めます。これを専門用語で「殺青」と言います。
釜炒り茶はこの殺青を釜で行ったお茶のことで、昔は熊本市近郊でも
農家の庭先などで、自家用に釜炒り茶を作っていました。

昔は上の写真のように手で炒って作りましたが、今は「炒り葉機」という
機械で炒り、揉みと乾燥も機械でします。
全国的に見れば、現在作られているお茶の99%は蒸気で蒸して作る煎茶
などのお茶になってしまっており、釜炒り茶は希少なお茶になってしまいました。
なぜ希少なお茶になったかというと、釜炒り茶が持っている商品特性が、
今の消費者が求める価値感に合わなくなってしまったから、と言うしか
ありません。
具体的には、出した時のお湯の色が黄色っぽく、薄いということがあります。お茶を飲む時にはその色も重要な評価の要素になります。

それから、味の薄さもあります。蒸気で蒸したお茶は熱のため
比較的中まで細胞膜が破壊されており、そのため内部のアミノ酸などの
成分が出てきやすくなっています。
またお湯の色も緑が濃くなります。釜炒り茶はその反対なわけです。
しかし良い点もあります。香りが良く、あっさりした味であることです。
釜で炒った独特の釜香(かまか)があります。
また、一部で釜炒り茶を見直そうという動きもあります。

先日行われました全国お茶まつり熊本大会の中でも「釜炒り茶フォーラム」
という形で討論会が行われました。
釜炒り茶フォーラムの報告はこちら→●
釜炒り茶は九州で、特に多く作られています。
熊本県の山都町から宮崎県の五ヶ瀬にいたる地方と天草地方、それと
佐賀県の嬉野が産地として有名です。
一説によると15世紀ごろに渡来した中国人によって九州地方に
釜炒り製法が伝わったといわれていますし、それ以前に釜で炒って作る
お茶があったともいわれています。
そのような釜炒り茶は色々な課題をかかえながらも一部の生産家たちに
よって作り続けられています。
当店では私が、釜炒り茶の香りと、煎茶の色、味をともに生かしたお茶を
作ろうと考えました。そしてブレンドにより両方の長所を生かして
「かおりっ子」というお茶を作りました。

「かおりっ子」100g 525円
本当は釜炒りだけのお茶を出したいのですが、総合評価でどうしても
落ちるので、売れ残ってしまいます。
もっと香りに特徴のある釜炒り茶がほしい~。
と思っているのです。
(追伸)
釜炒り茶については価値を認めて、広めたいという気持ちは大いにあるの
ですが、現実の製品とのギャップがあります。それだけ製造が難しいという
こともあるかも知れませんが、もどかしさもあります。

釜入家ファミリー。
シャイな一家である。

2008年10月31日
お茶のことわざ
昔からお茶は朝から飲むとよい、と言われてきました。
これはお茶の中に含まれるカフェインが目を覚まさせ
頭をシャキーンとさせる効果があることを昔の人が
経験から知っていたせいでしょう。

ことわざでも朝茶は三里帰ってでも飲め
ということわざがあります。飲み忘れたら、あとがえってでも飲みなっしぇ
ということです。
ことわざと言えばお茶の子さいさいという
言葉があります。お茶の子というのは、お茶の時に添えて出す
簡単なお菓子のことです。さいさいというのははやし言葉の
一種で俗謡の「のんこさいさい」からきたそうです。
つまり、簡単に食べられるから、簡単に出来ることをいいます。
さらにお茶の子というのは朝飯前に食べる軽食(お団子とか)
なんかもそう呼んだそうです。なぜ朝飯前に軽食を食べるんだ?
と思った人は昔のお百姓さんの苦労を知りませんね。
昔の農家は日の出とともに起き、朝飯前に一仕事をしてたんです。
だから「朝飯前」という言葉もそこから出たのです。
とかなんとか言ってお茶を濁して終わろうと思ったのですが
お茶を濁すの意味も一応押さえときましょう。
これは昔、抹茶を点てる作法をよく知らない者が知ったかぶりをして
アゴをたたいていたら「じゃあやってみろ」となり、実際に抹茶を
点てなければならないはめになっちゃった。狼狽していいかげんな
点てかたをしたら「濁らしているだけじゃないか」と言われて
ショボーン。
そこからその場だけをとりつくろうことを指して言うようになりました。
このブログはお茶を濁しているばかりではないのです。
お茶を濁すこともありますが・・。

なにをむきになってお茶を濁しているんだ。目が血走っているぞ。
奥さんにそんなに怒られたのか?

これはお茶の中に含まれるカフェインが目を覚まさせ
頭をシャキーンとさせる効果があることを昔の人が
経験から知っていたせいでしょう。

ことわざでも朝茶は三里帰ってでも飲め
ということわざがあります。飲み忘れたら、あとがえってでも飲みなっしぇ
ということです。
ことわざと言えばお茶の子さいさいという
言葉があります。お茶の子というのは、お茶の時に添えて出す
簡単なお菓子のことです。さいさいというのははやし言葉の
一種で俗謡の「のんこさいさい」からきたそうです。
つまり、簡単に食べられるから、簡単に出来ることをいいます。
さらにお茶の子というのは朝飯前に食べる軽食(お団子とか)
なんかもそう呼んだそうです。なぜ朝飯前に軽食を食べるんだ?
と思った人は昔のお百姓さんの苦労を知りませんね。
昔の農家は日の出とともに起き、朝飯前に一仕事をしてたんです。
だから「朝飯前」という言葉もそこから出たのです。
とかなんとか言ってお茶を濁して終わろうと思ったのですが
お茶を濁すの意味も一応押さえときましょう。
これは昔、抹茶を点てる作法をよく知らない者が知ったかぶりをして
アゴをたたいていたら「じゃあやってみろ」となり、実際に抹茶を
点てなければならないはめになっちゃった。狼狽していいかげんな
点てかたをしたら「濁らしているだけじゃないか」と言われて
ショボーン。
そこからその場だけをとりつくろうことを指して言うようになりました。
このブログはお茶を濁しているばかりではないのです。
お茶を濁すこともありますが・・。

なにをむきになってお茶を濁しているんだ。目が血走っているぞ。
奥さんにそんなに怒られたのか?

2008年10月30日
お茶の冷蔵
茶店ではお茶をどのように保存しているか知っていらっしゃいますか。
昔は木の茶箱にそのまま入れて保存していました。
冷蔵倉庫などない昔の話しです。
50~60kgはありそうな大きな茶箱をいくつも積み重ねて置くわけです。
そのための倉を作ったりもしました。
下の写真はディスプレイ用の小さな茶箱です。

15年くらい前までは「衣装保管に使うから、古い茶箱ないですか」と
聞かれることもあったのですが、最近はホームセンターなどにある
プラスチックの衣装ケースが軽くて、安くなったので、茶箱を聞かれる
こともなくなりました。
昔の茶箱は内側にブリキが貼ってあり、防湿性にすぐれていました。
しかし、どんなに防湿性がすぐれていると言っても、やはり中には
空気が入っています。酸化があります。お茶にとって酸化は、
味、香りが変わる元なのです。
だから昔のお茶は季節と共に風味が変わってきました。
基本的には古茶臭といって、すねたような臭いに変化していくのですが、
ある時期だけには熟成臭というか、ぷーんと香りたつようになる
時期があるのです。その時期がちょうど夏から秋にかけてでした。
でした、というのは、今はもうそのような保存はしないからです。
今はアルミの包材にいれて、空気を抜いて、ダンボール箱に入れ、
さらにそれを冷蔵倉庫で保存します。
酸化による製品劣化を防ぐためです。
新茶の時の新鮮さを失わないようにです。
基本的には劣化はありませんが、お茶自体に含まれている酸素の影響で
少しの変化はあります。
新茶時に渋かったお茶が年を越して飲んでみると、マイルドに変わる
こともたまにあります。

(これは当店の冷蔵倉庫の中、これは狭いほうです)
マイナス20℃くらいの冷凍で保存する倉庫もあり、そのように保存
されたお茶はまったくと言っていいほど変化しません。

(一度扉を開けたから12℃まであがってしまいました。いつもは8℃くらい)
だから乾燥製品でもあるお茶は、真空パックされた大袋を、さらに
100gとか200g袋に詰め替え、その時点で賞味期限を打ちます。
このように保存技術が進むと品質が良いまま維持できるので、
素晴らしいことには間違いありません。
しかし一つ欠点が・・それは、昔は季節とともに酸化が進み
丸一年目には古茶臭のピークを迎えちょうどその時、新茶の
なんとも言えない新鮮な香りをかぐのです。
新茶のおいしさが本当に身にしみたと思います。
でも新鮮なまま保存できる現代では新茶のインパクトは昔ほどない、
といってもいいでしょう。
一年中均一な品質のお茶が飲める今と、時と共に劣化していくお茶を
飲んでいた昔。でも新茶には真の感動があった昔。
さあ、どっちがいいのでしょう。

うるさいやつは冷凍保存しておくにかぎる。

昔は木の茶箱にそのまま入れて保存していました。
冷蔵倉庫などない昔の話しです。
50~60kgはありそうな大きな茶箱をいくつも積み重ねて置くわけです。
そのための倉を作ったりもしました。
下の写真はディスプレイ用の小さな茶箱です。

15年くらい前までは「衣装保管に使うから、古い茶箱ないですか」と
聞かれることもあったのですが、最近はホームセンターなどにある
プラスチックの衣装ケースが軽くて、安くなったので、茶箱を聞かれる
こともなくなりました。
昔の茶箱は内側にブリキが貼ってあり、防湿性にすぐれていました。
しかし、どんなに防湿性がすぐれていると言っても、やはり中には
空気が入っています。酸化があります。お茶にとって酸化は、
味、香りが変わる元なのです。
だから昔のお茶は季節と共に風味が変わってきました。
基本的には古茶臭といって、すねたような臭いに変化していくのですが、
ある時期だけには熟成臭というか、ぷーんと香りたつようになる
時期があるのです。その時期がちょうど夏から秋にかけてでした。
でした、というのは、今はもうそのような保存はしないからです。
今はアルミの包材にいれて、空気を抜いて、ダンボール箱に入れ、
さらにそれを冷蔵倉庫で保存します。
酸化による製品劣化を防ぐためです。
新茶の時の新鮮さを失わないようにです。
基本的には劣化はありませんが、お茶自体に含まれている酸素の影響で
少しの変化はあります。
新茶時に渋かったお茶が年を越して飲んでみると、マイルドに変わる
こともたまにあります。

(これは当店の冷蔵倉庫の中、これは狭いほうです)
マイナス20℃くらいの冷凍で保存する倉庫もあり、そのように保存
されたお茶はまったくと言っていいほど変化しません。

(一度扉を開けたから12℃まであがってしまいました。いつもは8℃くらい)
だから乾燥製品でもあるお茶は、真空パックされた大袋を、さらに
100gとか200g袋に詰め替え、その時点で賞味期限を打ちます。
このように保存技術が進むと品質が良いまま維持できるので、
素晴らしいことには間違いありません。
しかし一つ欠点が・・それは、昔は季節とともに酸化が進み
丸一年目には古茶臭のピークを迎えちょうどその時、新茶の
なんとも言えない新鮮な香りをかぐのです。
新茶のおいしさが本当に身にしみたと思います。
でも新鮮なまま保存できる現代では新茶のインパクトは昔ほどない、
といってもいいでしょう。
一年中均一な品質のお茶が飲める今と、時と共に劣化していくお茶を
飲んでいた昔。でも新茶には真の感動があった昔。
さあ、どっちがいいのでしょう。

うるさいやつは冷凍保存しておくにかぎる。

2008年10月29日
藤原さんの矢部茶

平成の大合併で色々な自治体がまとまり、大きな市や町になりました。
それはそれで良いことなのでしょうが、昔なじみの町名や村名が
少しずつ使われなくなっていくのは寂しい気もします。
旧上益城郡矢部町は合併により、山都町に変わりました。
矢部という地名はなくなりましたが、「矢部茶」という名前は
残っています。
矢部地方は古くからお茶作りが盛んな地方です。
もともとは釜炒り茶を作る農家が多かったのですが、最近は
玉緑茶(たまりょくちゃ)と呼ばれる蒸し製のお茶が主流に
なっています。
この地方は全般的に標高も割と高く、昼夜の寒暖の差があるので
渋味のはっきりとした味のお茶が作られます。
当店でお付き合いがあるのは旧矢部町の藤原徳門さんです。
藤原さんの茶園はとても管理が行き届いた美しい茶園です。

この藤原さんのお茶はきれいに丸まった形をしており、急須で
出すと濃く出ます。味は甘みと渋味がバランスよくまとまり
お茶本来の味を楽しむことが出来ます。

当店ではこのお茶を「藤原徳門さんの矢部茶」と名前をつけて
販売しております。
矢部茶が飲んでみたい。と思われた時にはいかがでしょうか。

90g入り 980円

2008年10月28日
玉露かりがね
秋の気配が次第に濃くなってきました。
これからだんだんお茶がおいしく感じられる季節になってきます。
新茶の頃のお茶もおいしいけれど、夏を越えて秋の今に時期になり
お茶はさらに熟成されてまろやかさを増します。
今日はこの時期にふさわしい「玉露かりがね」を紹介したいと思います。

かりがねというのは茎のことを言います。
クキが持つ風味ある香りが、玉露の甘みと相まって、独特の味わいを
生み出します。

さて、玉露というのはどんなお茶かご存知でしょうか。
玉露の茶園は普通の煎茶園と違い、摘む20日ほど前からワラで覆い、
日光を遮って育てます。

光を抑えることにより、葉の中のアミノ酸が渋くならず、うま味の
ある状態で摘むことが出来るのです。
この玉露のクキをメインにして作った玉露かりがねのおいしいいれ方を
説明してみたいと思います。
まず、お茶の葉は通常よりやや多目に取り急須に入れます。

お湯を湯飲みで冷まします。温度は約60℃くらい。
お湯の量は少な目がポイントです。

そして温度を下げたお湯を急須に入れ、フタをして約1.5分から2分くらい
待ちます。この待つ時間が大事です。
最後に湯飲みに注ぎますが、複数の湯飲みに注ぐ時はゆっくり交互に
注ぎ分けます。そして最後の一滴まで注ぎ切ることが大事です。

さて、そうやっていれたお茶は格別の味がします。
秋の日のゆったりとした一日にこのようなお茶を一服するのはいかがでしょうか。

玉露かりがね
80g入りで980円

秋の日に一服しながらしみじみ
俺も昔はイケメンでもてたものだ・・と

これからだんだんお茶がおいしく感じられる季節になってきます。
新茶の頃のお茶もおいしいけれど、夏を越えて秋の今に時期になり
お茶はさらに熟成されてまろやかさを増します。
今日はこの時期にふさわしい「玉露かりがね」を紹介したいと思います。

かりがねというのは茎のことを言います。
クキが持つ風味ある香りが、玉露の甘みと相まって、独特の味わいを
生み出します。

さて、玉露というのはどんなお茶かご存知でしょうか。
玉露の茶園は普通の煎茶園と違い、摘む20日ほど前からワラで覆い、
日光を遮って育てます。

光を抑えることにより、葉の中のアミノ酸が渋くならず、うま味の
ある状態で摘むことが出来るのです。
この玉露のクキをメインにして作った玉露かりがねのおいしいいれ方を
説明してみたいと思います。
まず、お茶の葉は通常よりやや多目に取り急須に入れます。

お湯を湯飲みで冷まします。温度は約60℃くらい。
お湯の量は少な目がポイントです。

そして温度を下げたお湯を急須に入れ、フタをして約1.5分から2分くらい
待ちます。この待つ時間が大事です。
最後に湯飲みに注ぎますが、複数の湯飲みに注ぐ時はゆっくり交互に
注ぎ分けます。そして最後の一滴まで注ぎ切ることが大事です。

さて、そうやっていれたお茶は格別の味がします。
秋の日のゆったりとした一日にこのようなお茶を一服するのはいかがでしょうか。

玉露かりがね
80g入りで980円

秋の日に一服しながらしみじみ
俺も昔はイケメンでもてたものだ・・と

2008年10月25日
秋の山茶園
秋も深まりつつある1日、お茶の仕入れを兼ね、山鹿市鹿北にある
茶園の様子を見に行きました。
ここ、鹿北地方は江戸時代からお茶作りの盛んなところで、
良質のお茶が採れます。

中山間地の山あいに茶園を切り開く場合が多く、一つの茶園の面積が
あまり広く取れないので、効率に欠ける部分はありますが、
標高の高さから来るお茶の品質の良さには定評があります。
行ったときにはちょうど秋整枝(あきせいし)が行われているところでした。

秋製枝というのは、春に新芽を摘む時に古い葉を摘み取らないように
今のうちにきれいに形を整えておく作業のことです。
これから寒くなる時期はお茶の木を休ませる期間になります。
ゆっくり十分に休ませると春においしい芽が伸びて来るのです。

このように山あいを縫って茶畑が広がっています。
ここに来ると本当に心がほっと安らぎます。

お茶の倉庫があるところまで下ってきたら、おや、なんだあの雲は!

山の頂上からまるで煙が立ち上っているみたい。いや、天から落ちた
雷のような雲なのか。
この雲、東から西に空を横切って伸びていました。ナンナノダロウ?
それはともかく、ほんの少しでしたが、山里の秋を感じることが
出来たひと時でした。

茶園の様子を見に行きました。
ここ、鹿北地方は江戸時代からお茶作りの盛んなところで、
良質のお茶が採れます。

中山間地の山あいに茶園を切り開く場合が多く、一つの茶園の面積が
あまり広く取れないので、効率に欠ける部分はありますが、
標高の高さから来るお茶の品質の良さには定評があります。
行ったときにはちょうど秋整枝(あきせいし)が行われているところでした。

秋製枝というのは、春に新芽を摘む時に古い葉を摘み取らないように
今のうちにきれいに形を整えておく作業のことです。
これから寒くなる時期はお茶の木を休ませる期間になります。
ゆっくり十分に休ませると春においしい芽が伸びて来るのです。

このように山あいを縫って茶畑が広がっています。
ここに来ると本当に心がほっと安らぎます。

お茶の倉庫があるところまで下ってきたら、おや、なんだあの雲は!

山の頂上からまるで煙が立ち上っているみたい。いや、天から落ちた
雷のような雲なのか。
この雲、東から西に空を横切って伸びていました。ナンナノダロウ?
それはともかく、ほんの少しでしたが、山里の秋を感じることが
出来たひと時でした。

2008年10月23日
ほうじ茶を作るっ
さぁ、今日は「ほうじ茶」作りです!
ナイストライの中学生2人にやってもらうぞー。
我が店の奥からコンパクトな「ほうじ機」をごそごそと
引っ張り出してきます。

これは電気ヒーターで熱しながら、同時にドラムを回転させ
中のお茶の葉を焙じる機械です。
中の温度は90℃~120℃くらいにします。
しばらく熱するとミニ煙突からなにやらモクモクとかすかな煙が
立ち上ってきます。

さぁ、そこへお番茶を入れて、GO!
ナイストライの2人に調整の仕方を教えて、「ほうじ番」をしてもらいます。
なにしろこのほうじ機はちょっと目を離すとすぐ焦げたり、生炒りだったり
するのです。

おや、2人で焙じを調整したりしながら、道行く人達にちゃんと「こんにちは」
と挨拶してるではないか。感心、感心。
ほうじ茶は強く炒るために葉が茶色になるし、出した時のお湯の色も茶色です。
でもとても香ばしい香りがするし、焙じる時にカフェインが蒸気と一緒に
飛ぶために、刺激の少ない、小さいお子さんや高齢者にやさしいお茶に
なります。

さぁ、できたヨ、君達も飲んでごらん。

そう、おいしい!?

何が原因か分からないが
自分を焙じてしまっている。
・・・コメントのしようがない。

ナイストライの中学生2人にやってもらうぞー。
我が店の奥からコンパクトな「ほうじ機」をごそごそと
引っ張り出してきます。

これは電気ヒーターで熱しながら、同時にドラムを回転させ
中のお茶の葉を焙じる機械です。
中の温度は90℃~120℃くらいにします。
しばらく熱するとミニ煙突からなにやらモクモクとかすかな煙が
立ち上ってきます。

さぁ、そこへお番茶を入れて、GO!
ナイストライの2人に調整の仕方を教えて、「ほうじ番」をしてもらいます。
なにしろこのほうじ機はちょっと目を離すとすぐ焦げたり、生炒りだったり
するのです。

おや、2人で焙じを調整したりしながら、道行く人達にちゃんと「こんにちは」
と挨拶してるではないか。感心、感心。
ほうじ茶は強く炒るために葉が茶色になるし、出した時のお湯の色も茶色です。
でもとても香ばしい香りがするし、焙じる時にカフェインが蒸気と一緒に
飛ぶために、刺激の少ない、小さいお子さんや高齢者にやさしいお茶に
なります。

さぁ、できたヨ、君達も飲んでごらん。

そう、おいしい!?

何が原因か分からないが
自分を焙じてしまっている。
・・・コメントのしようがない。

2008年10月19日
もう年末の準備
10月の半ばを過ぎたのに、昼間は暑いですね。
なんだか時が逆戻りしている感じですが、ちゃんと月日は過ぎています。
早くも今年の年末に向けての「茶袋」のデザインを選ばなくては
なりません。早いですね~。

来年は丑年(うしどし)です。
十二支を全部言えますか?
子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
干支というのは本来十二支と十干が組み合わさったものだそうです。
十干は 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸 からなるものです。
干支の組み合わせは60通りあるそうで、
来年はその中の26番目の己丑(つちのとうし)だそうです。
さぁ、来年はいい年になってくれるかな。

今から牛の着ぐるみを試着して、
一体正月に何をしようというのだ。

なんだか時が逆戻りしている感じですが、ちゃんと月日は過ぎています。
早くも今年の年末に向けての「茶袋」のデザインを選ばなくては
なりません。早いですね~。

来年は丑年(うしどし)です。
十二支を全部言えますか?
子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
干支というのは本来十二支と十干が組み合わさったものだそうです。
十干は 甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸 からなるものです。
干支の組み合わせは60通りあるそうで、
来年はその中の26番目の己丑(つちのとうし)だそうです。
さぁ、来年はいい年になってくれるかな。

今から牛の着ぐるみを試着して、
一体正月に何をしようというのだ。

2008年10月17日
バンチャについて。
「バンチャ」ってどんなお茶かご存知ですか。
普通は番茶と書きます。
一般的には最初のお茶を摘み取った後に伸びてくる
固く大きくなった葉で作ったお茶で、下級茶の総称として
使われることが多いようです。最初に摘むお茶を1番茶といい、
その後の2番茶、3番茶を使用することから、番茶と呼ばれる
ようです。夏の日差しをたくさん浴びて、ざっくり大きめの
葉っぱで、やや渋めのお茶です。
もう一つは晩茶と記述すべきお茶があります。
これは、日本各地に伝わる土着のお茶のことで、様々な種類が
あります。晩茶の晩は、遅いなどの意味があり、
1番茶を遅く摘んで作るのですが、土着のお茶だけあり、
私たちが通常目にしない意表をつく姿かたちのお茶があります。


この茶色の異様なお茶は富山県の朝日町(旧名)で作られる
「バタバタ茶」と呼ばれるお茶です。
バタバタとはいかにも面白い名前です。これはその飲み方に
関係があるようです。
このお茶は煮出した後に、大き目の茶せん
(竹の先の細かく切れ目を入れたもの)
で泡立てて飲むお茶なのです。その泡立てる様子がせかせかと
あわただしい様子なのでこの名前が付いたそうです。
そしてこのお茶の大きな特色は中国で飲まれる黒茶(プーアル茶などの
後発酵茶)と同じ仲間で、乳酸発酵をさせています。
プーアール茶といえば、一時期ダイエットにも良いといわれたお茶。
このバタバタ茶はかなり古くからあり、煎茶よりもずっと歴史があります。
一説によると縄文時代に中国から伝わったとも言われています。
とてもユニークなこのお茶、少々酸味があり、普通のお茶とは
まったく違う味ですが、ユニークゆえに注目もされ、最近は缶入り
ドリンクも出たそうです。

普通じゃない、面白晩茶、
このバタバタ茶だけではないのです。 また次に紹介します。

バタバタとしてるようだが、
実はのどかな秋の一日

普通は番茶と書きます。
一般的には最初のお茶を摘み取った後に伸びてくる
固く大きくなった葉で作ったお茶で、下級茶の総称として
使われることが多いようです。最初に摘むお茶を1番茶といい、
その後の2番茶、3番茶を使用することから、番茶と呼ばれる
ようです。夏の日差しをたくさん浴びて、ざっくり大きめの
葉っぱで、やや渋めのお茶です。
もう一つは晩茶と記述すべきお茶があります。
これは、日本各地に伝わる土着のお茶のことで、様々な種類が
あります。晩茶の晩は、遅いなどの意味があり、
1番茶を遅く摘んで作るのですが、土着のお茶だけあり、
私たちが通常目にしない意表をつく姿かたちのお茶があります。


この茶色の異様なお茶は富山県の朝日町(旧名)で作られる
「バタバタ茶」と呼ばれるお茶です。
バタバタとはいかにも面白い名前です。これはその飲み方に
関係があるようです。
このお茶は煮出した後に、大き目の茶せん
(竹の先の細かく切れ目を入れたもの)
で泡立てて飲むお茶なのです。その泡立てる様子がせかせかと
あわただしい様子なのでこの名前が付いたそうです。
そしてこのお茶の大きな特色は中国で飲まれる黒茶(プーアル茶などの
後発酵茶)と同じ仲間で、乳酸発酵をさせています。
プーアール茶といえば、一時期ダイエットにも良いといわれたお茶。
このバタバタ茶はかなり古くからあり、煎茶よりもずっと歴史があります。
一説によると縄文時代に中国から伝わったとも言われています。
とてもユニークなこのお茶、少々酸味があり、普通のお茶とは
まったく違う味ですが、ユニークゆえに注目もされ、最近は缶入り
ドリンクも出たそうです。

普通じゃない、面白晩茶、
このバタバタ茶だけではないのです。 また次に紹介します。

バタバタとしてるようだが、
実はのどかな秋の一日

2008年10月15日
茶缶くん
お茶缶です。

食卓上では地味な存在かもしれません。
和紙貼り缶が多く使われています。
桜の皮を身にまとったシャレ者もいます。
中はステンレス製で機密性を高めるために二重フタになっています。

お茶にとっては、空気に触れ合うことが一番大敵です。
まず、空気中の湿気を吸い取って、自身がしけってしまいます。
そして、酸素に触れて酸化を起こします。
これは食品全般に言えることですが、長い期間空気中に置いておくと
臭いが悪くなり、味も落ちてきます。
だから、なるべく空気をシャットアウトしたほうがいいのです。
お茶の品質を守るためがんばってきた「茶缶」くん。
最近はチャック式袋の増加で、活躍の場が減っています。

近頃キャンディボックスに使えそうなお茶缶も出てきました。



食卓上では地味な存在かもしれません。
和紙貼り缶が多く使われています。
桜の皮を身にまとったシャレ者もいます。
中はステンレス製で機密性を高めるために二重フタになっています。

お茶にとっては、空気に触れ合うことが一番大敵です。
まず、空気中の湿気を吸い取って、自身がしけってしまいます。
そして、酸素に触れて酸化を起こします。
これは食品全般に言えることですが、長い期間空気中に置いておくと
臭いが悪くなり、味も落ちてきます。
だから、なるべく空気をシャットアウトしたほうがいいのです。
お茶の品質を守るためがんばってきた「茶缶」くん。
最近はチャック式袋の増加で、活躍の場が減っています。

近頃キャンディボックスに使えそうなお茶缶も出てきました。